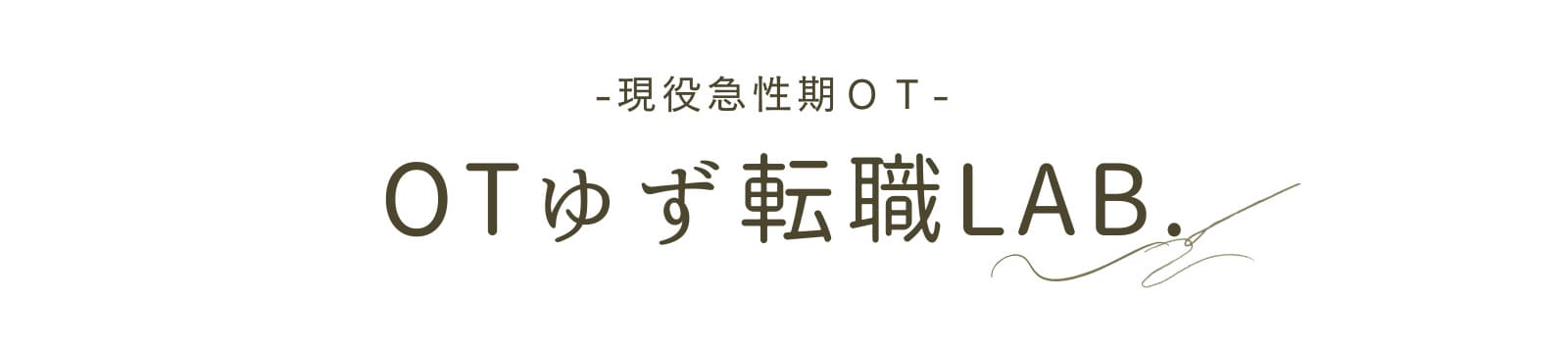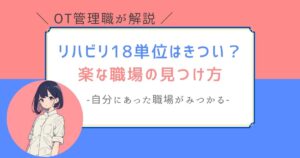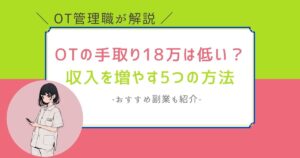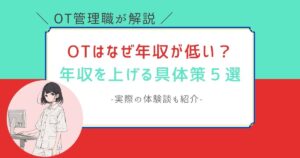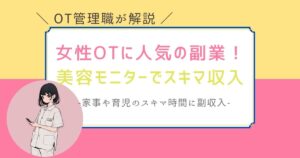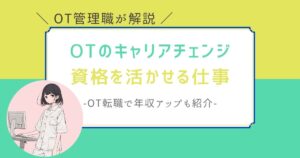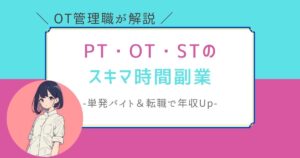急性期で働く作業療法士の中には、
 OT
OT体力的に限界を感じている



もっと1人の患者と関わる時間がほしい
と考え、回復期への転職を検討する方も多くいます。
しかし、業務内容や役割の違いや、
これまでの経験が活かせるのかといった疑問から、一歩踏み出せずにいる方も多いのではないでしょうか?
この記事では、
急性期から回復期へ転職する際に感じやすい不安を整理しつつ、
実際に転職することで得られる5つのメリットをわかりやすく解説。
さらに、転職後のギャップや成功のコツも紹介しています。



後悔のない選択をしたい方はぜひ参考にしてください。


- OT歴15年以上、急性期OT
- 役職名は、係長
- 転職歴2回
- 回復期→在宅→急性期(現在)
- 2回の転職で年収250万Up
- 面接対策・転職ノウハウを発信
- (@yuzu_ot_reha)


急性期から回復期へ転職したいOTが感じる不安とは?
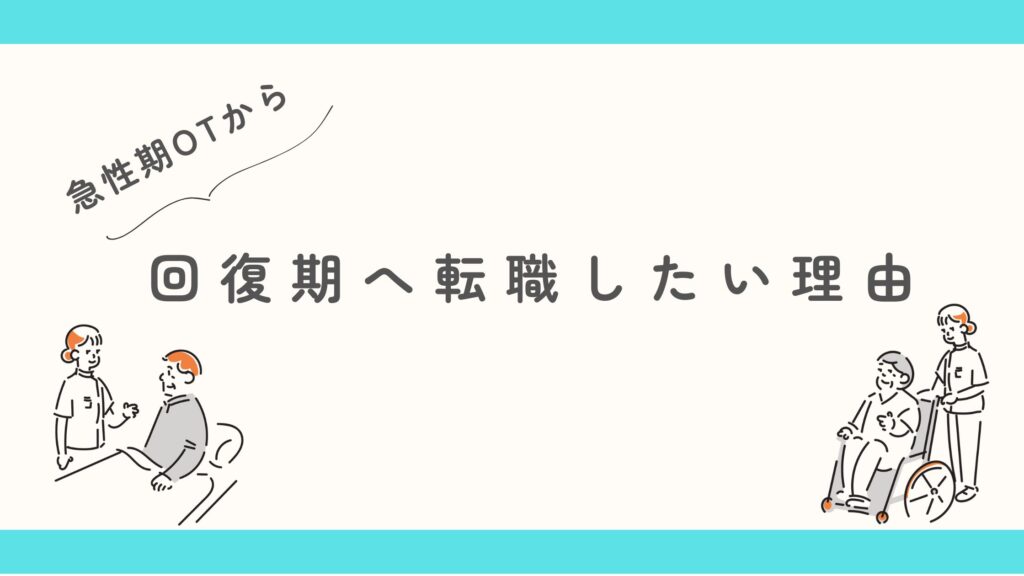
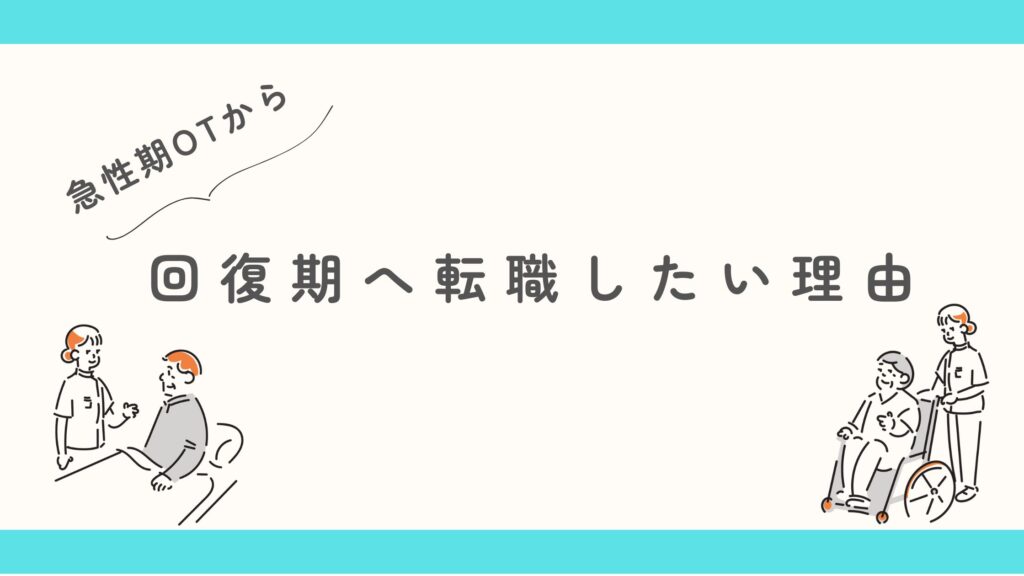
急性期から回復期へ転職を考える作業療法士は多くいますが、
その一方で転職に踏み切れない理由の多くは「環境の違い」に対する不安です。
- 急性期から離れることへの迷い
- スキルや評価の変化に対する不安
- 回復期で求められる役割の違い
ここでは、急性期から回復期へのキャリアチェンジを考える際に、よく聞かれる代表的な不安を整理します。
急性期から離れることへの迷い
急性期での経験が長いと、
「この現場でしか通用しないのでは?」という不安を感じがちです。
特に、1日何人もの患者に対応し、
スピードと判断力が求められる環境で働いてきた作業療法士ほど、



回復期に行ったら物足りなく感じるかも…
という迷いを抱くこともあります。
また、
- 急性期の経験が評価されるのか
- せっかく積んできた知識や技術がリセットされるかも
といった懸念も聞かれます。
しかし実際には、
転職を「マイナスの移動」ではなく、「フィールドの変化」として捉えることが重要です。
スキルや評価の変化に対する不安
評価法やアプローチのスタイルが変わることに不安を感じる方も多くいます。
急性期では、退院までの期間も短いため「短期で結果を出す力」が求められます。
一方、回復期では中長期的な目標設定とプロセスの観察・修正能力が求められるため、
業務の進め方そのものが大きく異なります。
この違いにより、
- 自分のやり方が通用しないかもしれない
- 今までのスキルが落ちるのでは
と感じる人もいます。
しかし、
現場に慣れるまで少し時間はかかりますが、学び直す意欲があれば十分対応可能です。
回復期で求められる役割の違い
回復期では、急性期以上に「チームの一員としての動き」が重視されます。
医師・看護師・リハ職・社会福祉士・管理栄養士など、
他職種との連携が密であるため、リーダーシップや調整力が必要になる場面も増えてきます。
また、患者さんと深く関わる時間が長くなる分、
精神的なサポートやご家族との連携・情報提供など、対人援助的な業務も増える傾向があります。
こうした役割の変化に、
「ついていけるか不安」「自分に向いているのか分からない」と感じる方も少なくありません。



事前に役割の違いを理解しておくことで、ギャップはかなり減らせます。
\あなたに合った職場が見つかる/
OTに人気の転職サイト3選急性期から回復期に転職する5つのメリット
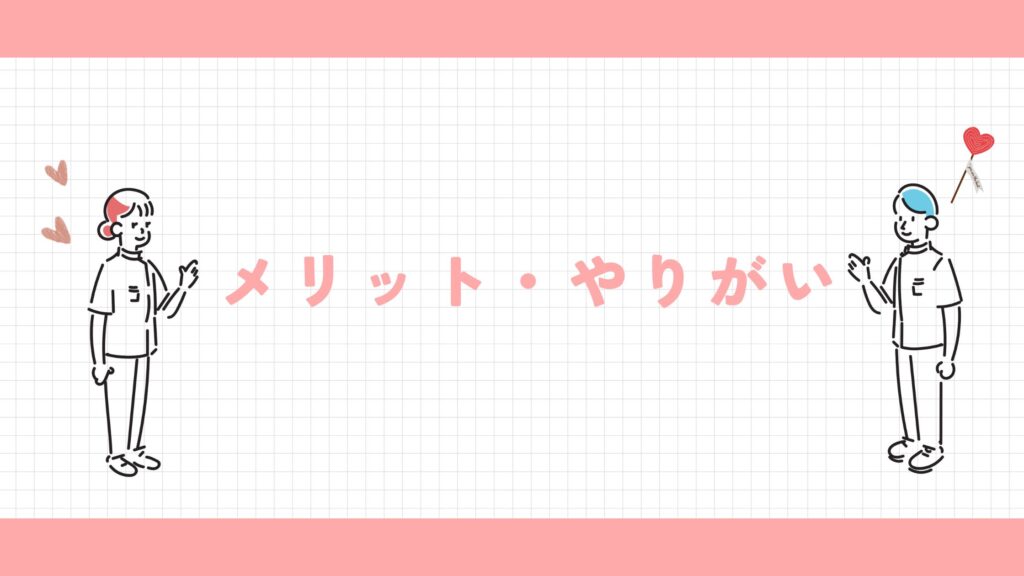
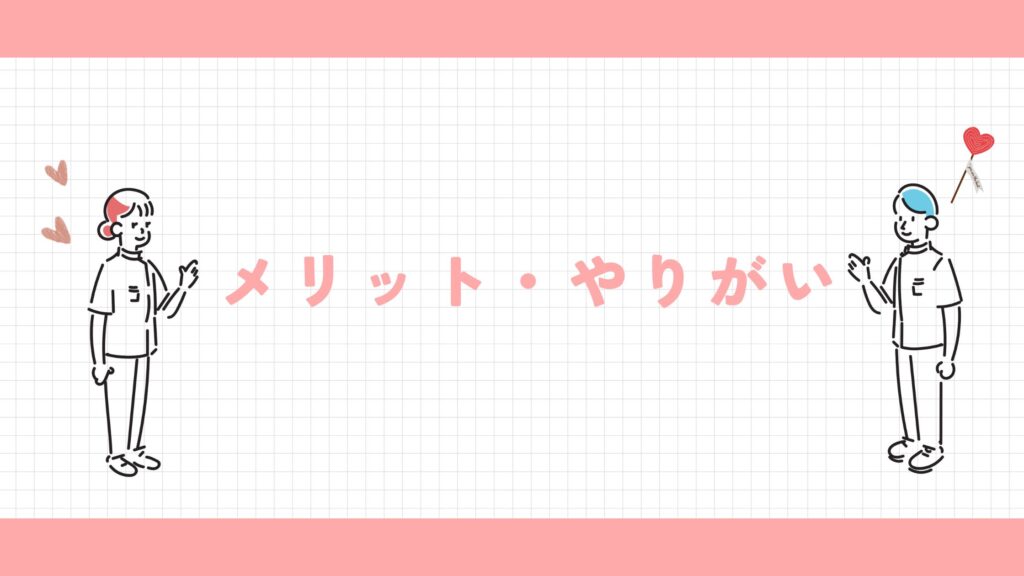
急性期から回復期への転職には、不安と迷いもつきものです。
しかし実際には、回復期ならではの働き方や価値観の中に、多くのメリットが存在します。
- ワークライフバランスが改善されやすい
- 患者と長く関われるやりがい
- 多職種との連携が深まり、学びが多い
- 教育的・心理的支援スキルが磨ける
- リハビリの全体像を理解するステップになる
ここでは、急性期での経験を土台に、
回復期で働くことによって得られる代表的な5つのメリットを紹介します。
ワークライフバランスが改善されやすい
急性期では、患者実数の多さや急変などにより、
残業が日常化している施設も少なくありません。
それに比べ、回復期では1日のスケジュールが安定しており、定時で退勤できる日が増える傾向があります。
- リハビリ時間があらかじめ決まっており、急な変更が少ない
- 患者の状態も比較的安定しており、業務の予測が立てやすい
- カンファレンスもルーチン化されていて、時間管理しやすい
これにより、家族との時間や趣味・副業の時間を確保しやすいです。



無理なく働き続けられる職場を見つけられた、と満足するOTも多数います。
患者と長く関われるやりがい
急性期では、患者と数回しか関わらずに退院を迎えることも珍しくありません。
回復期では平均して2〜3ヶ月程度の入院期間があるため、
患者の生活や精神面の変化までじっくり見守ることができます。
- 毎日のリハビリを通して、信頼関係が深まる
- 日常生活や社会復帰までの再構築に関われる
- 退院後の生活設計にも関与でき、OT専門性を実感できる
「患者さんとじっくり関わりたい」という想いが強いOTには、回復期はまさに最適なフィールドです。


多職種との連携が深まり、学びが多い
回復期では、退院支援や家屋改修、地域移行などに向けて、多職種との密な連携が不可欠です。
そのため、多職種とのチーム医療を日常的に体験できます。
- 多職種会議の参加頻度が高く、視野が広がる
- 役割分担を理解したうえで、専門性を発揮できる
- 他職種の考え方や制度面に対する理解も深まる
生活期への橋渡し役としての役割を感じられることが魅力だと語るOTも多くいます。
教育的・心理的支援スキルが磨ける
回復期は「機能回復」だけでなく、「心のサポート」も大切にされるステージです。
失語症や高次脳機能障害などの患者に対して、言語化できない不安や焦りに寄り添う力が必要になります。
- 患者の自己効力感を高める働きかけ
- モチベーション低下への対応
- 家族指導・心理的ケアも含めたアプローチ
急性期ではあまり求められなかった部分が、回復期では重要なスキルになります。
これにより、



より“人を支える”専門職としての力量が高まることを実感できます。
リハビリの全体像を理解するステップになる
急性期での経験があっても、
「患者の退院後の生活がどうなるのか」を知らないまま臨床を続けるOTも少なくありません。
回復期に転職することで、急性期・回復期・生活期の流れを実感として理解するチャンスになります。
- どのような支援が在宅復帰につながるのかが具体的に見える
- 急性期でのゴール設定にも活きる知見が増える
- 今後、訪問リハや地域リハに進む際の視野が広がる
「回復期を経験したことで、急性期の役割がより深く理解できるようになった」という声も多く、
“キャリア全体を見通す転機”としても有効な転職になります。
実際に転職して感じたギャップと対処法
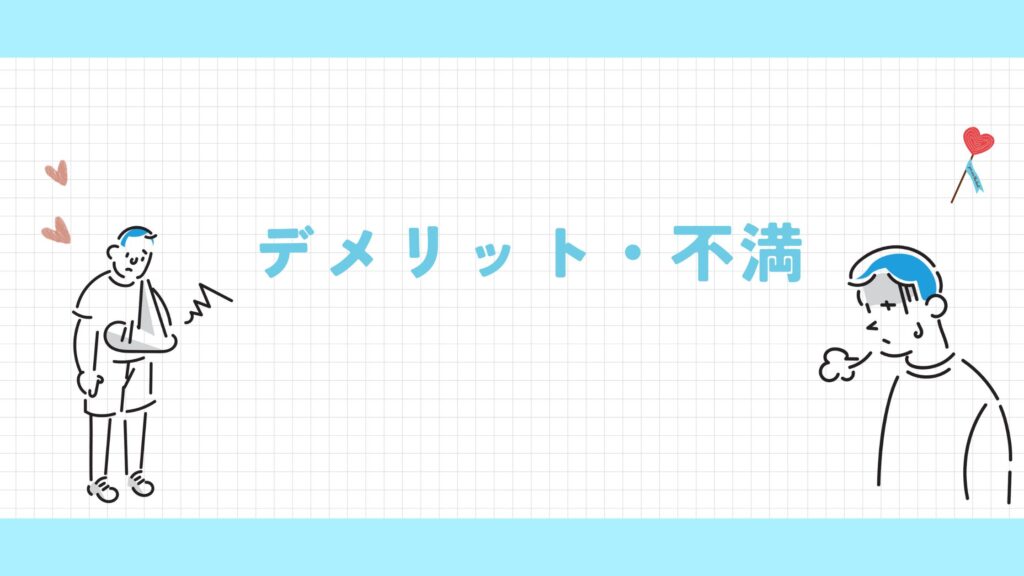
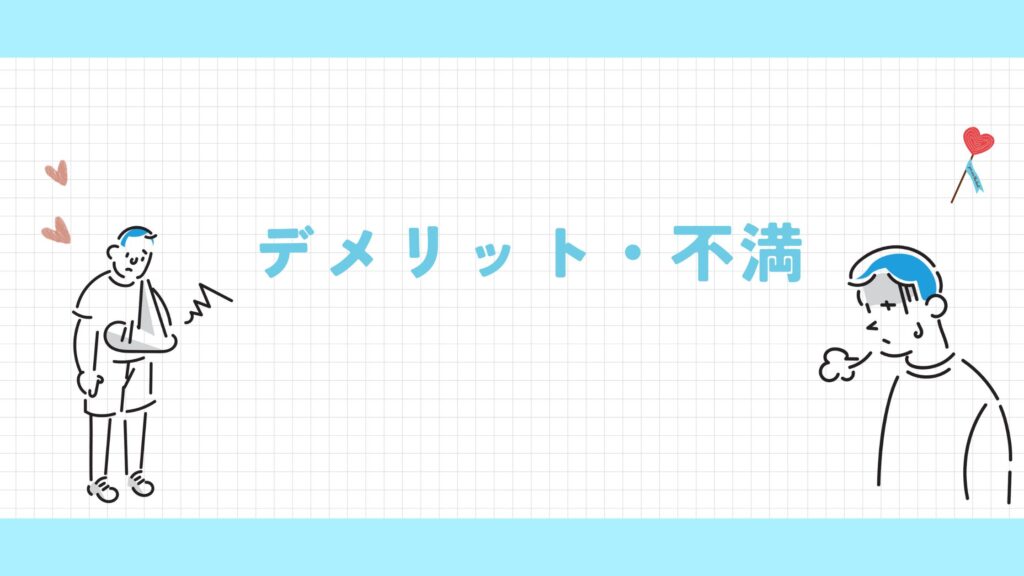
急性期から回復期へ転職すると、
想像以上に「職場の文化」や「役割の違い」に戸惑う場面があります。
- 業務量・評価制度の違いに戸惑う
- チーム内の役割やリズムの違いに慣れるまで
- 「急性期っぽさ」が浮いてしまうことも?
ここでは、実際に転職した作業療法士が感じた代表的なギャップと、うまく対応するための対処法を紹介します。
業務量・内容の違いに戸惑う
急性期では、1単位刻みで患者さんを多く介入することが多いです。
回復期では1人3単位で介入することも多く、初めは介入時間の違いに戸惑うことも多くあります。
また、回復期では患者介入以外に、
多職種カンファレンスや退院前訪問など急性期では関わることが少ない業務内容も多くあります。
チーム内の役割やリズムの違いに慣れるまで
急性期では、医師主導・指示に基づいた短時間・即応型の対応が多い一方で、
回復期ではOT自身がリーダー的に介入計画を立てることが求められる場面が増えます。
また、リハ職間での連携やすり合わせの機会も増えるため、コミュニケーション能力や発言力も重要になってきます。
これに対して、
「自分の提案が通らない」
「他職種との話し合いが難しい」
と感じる人もいますが、



継続的に参加・発信をすることで自然と動けるようになります。
「急性期っぽさ」が浮いてしまうことも?
急性期は日々スピード感が求められます。
そのため、回復期でのスピード感とのギャップに違和感を感じるケースもあります。
- リハ時間の進め方が早すぎて、PTSTとのペースがズレる
- 報告や記録がやたらと簡潔すぎて、現場の雰囲気と合わない
- チーム会議で「内容が薄い」と感じられることも
こうしたズレは、悪いことではありませんが、
「まずは受け入れて合わせる」姿勢を意識することが円滑な関係の第一歩になります。



スピードよりプロセス重視のマインドに切り替えることがポイントです。
\その一歩が未来を変える!/
OTに人気の転職サイト3選転職を成功させるためのチェックポイント
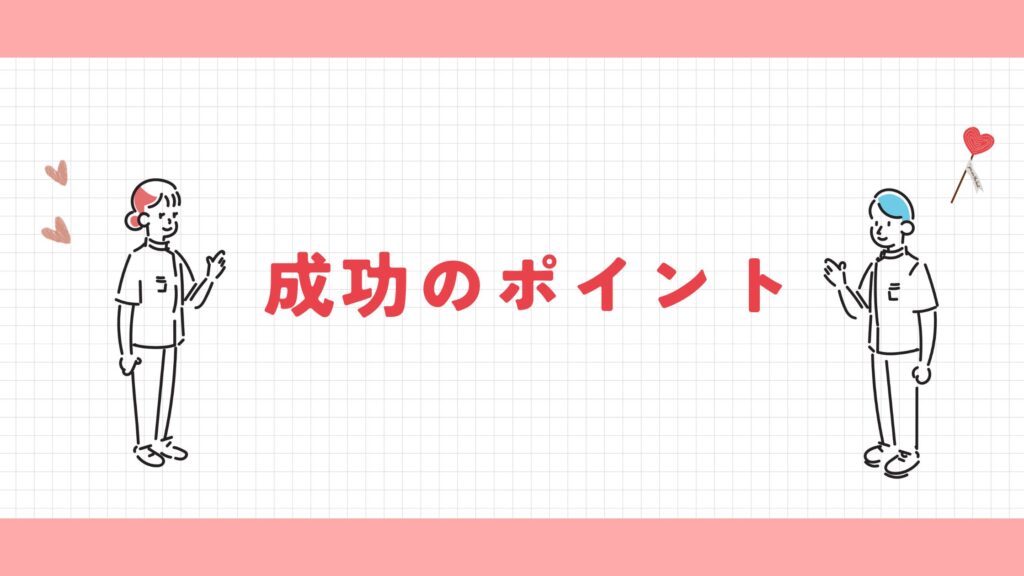
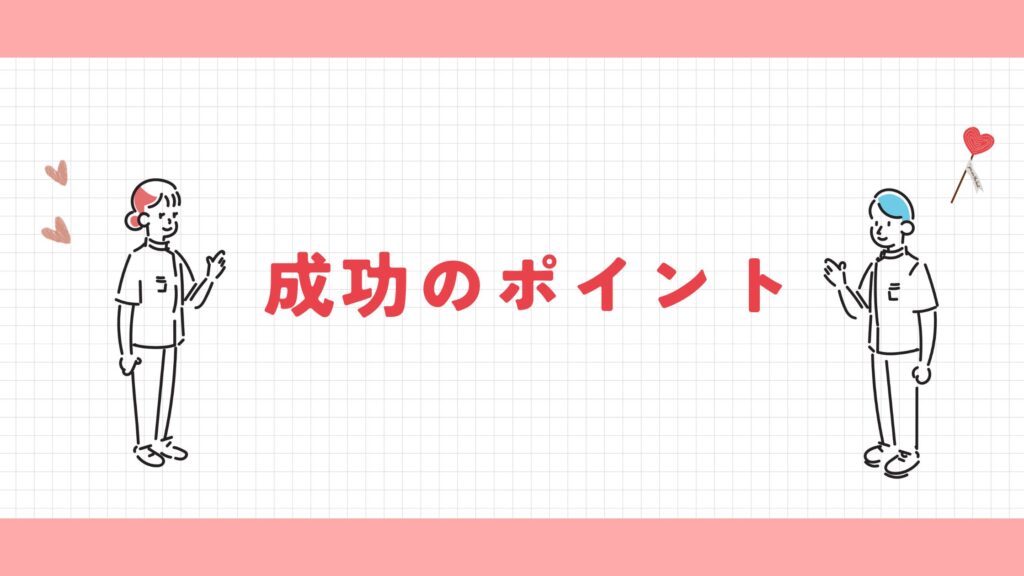
急性期から回復期への転職を成功させるには、「現場に合った転職活動」が必要不可欠です。
- 求人票で見るべきポイント
- 面接・見学で確認しておきたいこと
- 転職エージェントを利用
ここでは、転職先を選ぶ際に見ておくべき具体的なポイントと、ミスマッチを防ぐための方法を紹介します。
求人票で見るべきポイント
求人票には「残業なし」「教育体制あり」などの魅力的な文言が並びますが、曖昧な表現に注意が必要です。
以下の点をチェックしておきましょう。
| チェック項目 | 確認する理由 |
|---|---|
| リハビリ対象者・疾患構成 | 脳血管中心か、整形中心かで仕事内容が大きく異なる |
| 平均在院日数 | リハの進行スピードや期間設定に関わる |
| リハスタッフの人数・構成比 | OTの役割が明確に分担されているかどうか |
| 1日の平均単位数・担当患者数 | 業務量のイメージ/過度なノルマがないか |
| カンファレンスの頻度・方法 | チーム連携/残業につながる頻度かどうかの見極め |
特に「教育体制あり」などの文言には、「見学・面談で実際の取り組みを聞くこと」が大切です。


面接・見学で確認しておきたいこと
求人票では見えない情報は、面接や見学時の質問で掘り下げることが有効です。
- 「急性期出身のスタッフは何名くらいいますか?」
- 「1日のリハの流れを教えてください」
- 「カンファレンスや会議の時間配分はどうなっていますか?」
- 「新人研修やOJTのサポート体制はどうですか?」
こうした具体的な質問を通して、



「入職後のギャップをいかに減らすか」が転職成功のカギになります。


転職エージェントを利用
急性期→回復期への転職は、転職エージェントを通すと交渉がスムーズになります。
| 活用ポイント | メリット |
|---|---|
| 希望条件 | 自分の希望(残業なし・教育重視など)を言語化できる |
| 非公開求人の紹介 | 回復期に強い求人や、急性期出身者歓迎の職場なども見つけやすい |
| 書類・面接対策のサポート | 回復期で求められる視点で履歴書や面接のアドバイスを受けられる |
| 内部の情報共有 | 実際に転職した人の声や、人間関係・退職理由などの裏側も教えてくれる場合がある |
エージェントを使うことで、「自分に合った環境か」を客観的に見極める手助けになります。
特に、
- PTOT人材バンク
- レバウェルリハビリ
- PTOTSTワーカー
の3社は、回復期転職の事例も多くおすすめです。


まとめ|急性期での経験を強みにして回復期で活躍しよう
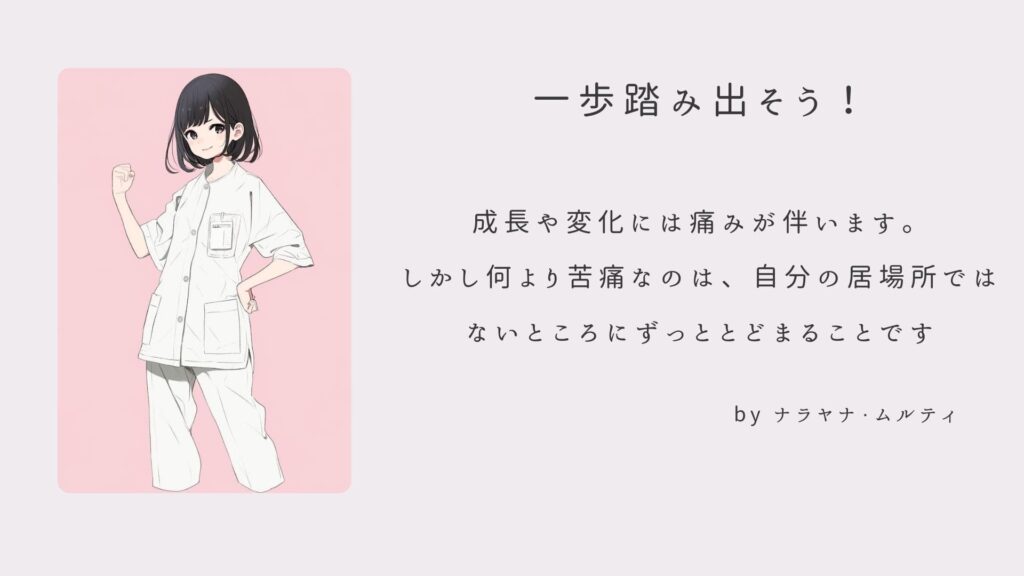
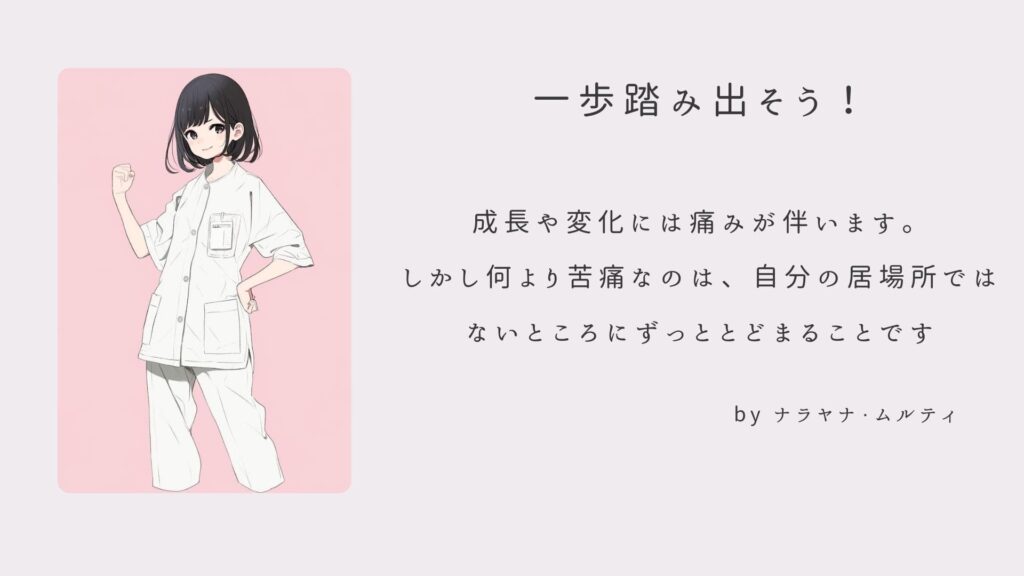
急性期から回復期への転職は、不安と期待が入り混じる選択かもしれません。
しかし、急性期で培った観察力・判断力・迅速な対応力は、回復期の現場でも十分に活かすことができます。
焦らず、丁寧に職場を選び、
自分の強みを活かせる現場で次の一歩を踏み出してみてください。
\ 回復期に強い求人も掲載中! /
OTにおすすめの転職サイト3選を見る急性期で頑張ってきたあなたなら、回復期でも必ず必要とされる存在になれます。



次のステージでも、あなたらしく活躍できることを応援しています。