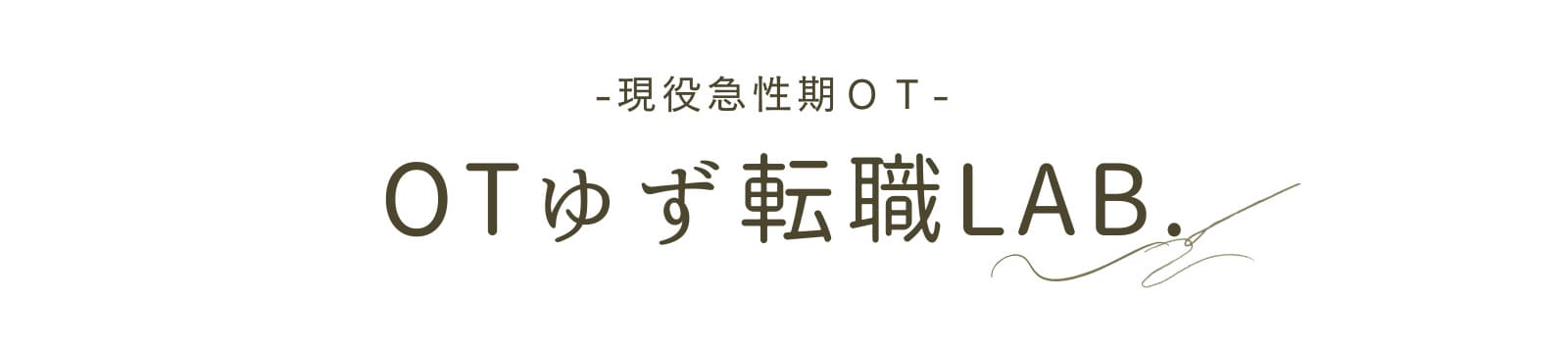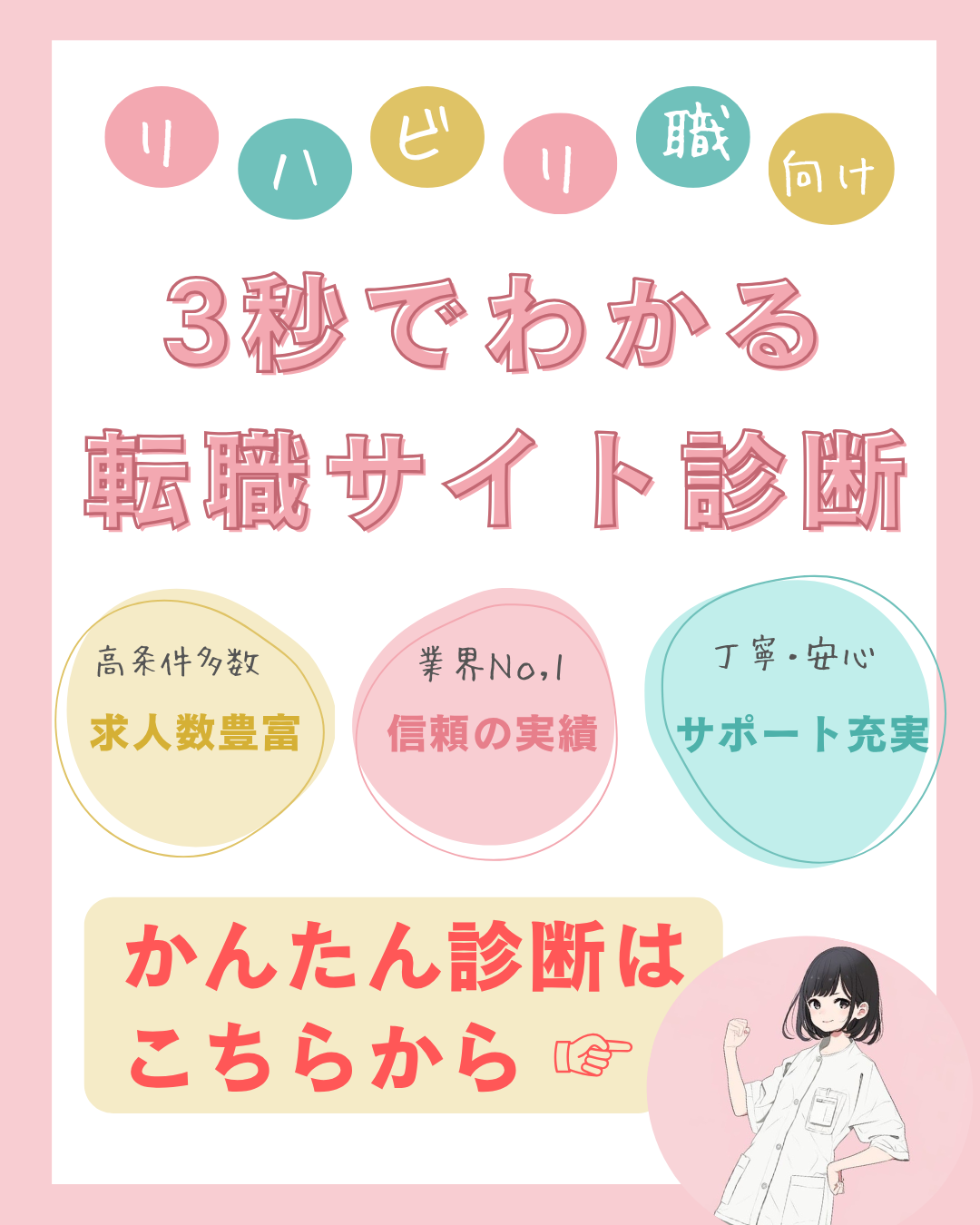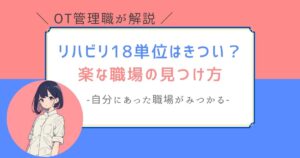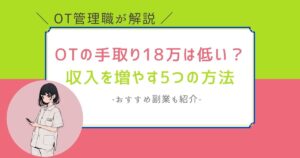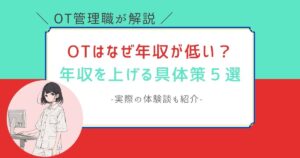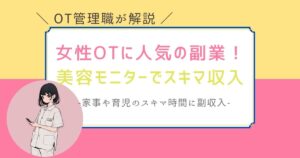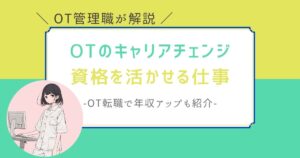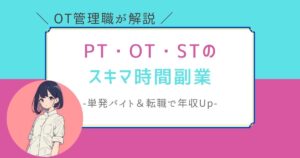辞めたいOT
辞めたいOTOTから公務員ってなれるの?



公務員の方が安定して稼げそう。
作業療法士として働きながら、「このままでいいのかな?」と感じる瞬間はありませんか?
医療現場の疲労や将来への不安から、
“公務員”というセカンドキャリアに興味を持つ方が、いま確実に増えています。
この記事では、
OTから公務員になるための現実的なルートや、
実際に選ばれている理由、向いている人の特徴までを現役作業療法士の視点で詳しく解説します。
安定・社会的信用・長期的なキャリア設計。



あなたの経験をどう活かせるか、一緒に考えていきましょう。


- OT歴15年以上、急性期OT
- 役職名は、係長
- 転職歴2回
- 回復期→在宅→急性期(現在)
- 2回の転職で年収250万Up
- 面接対策・転職ノウハウ情報を発信
作業療法士が公務員を目指す人が増えている理由
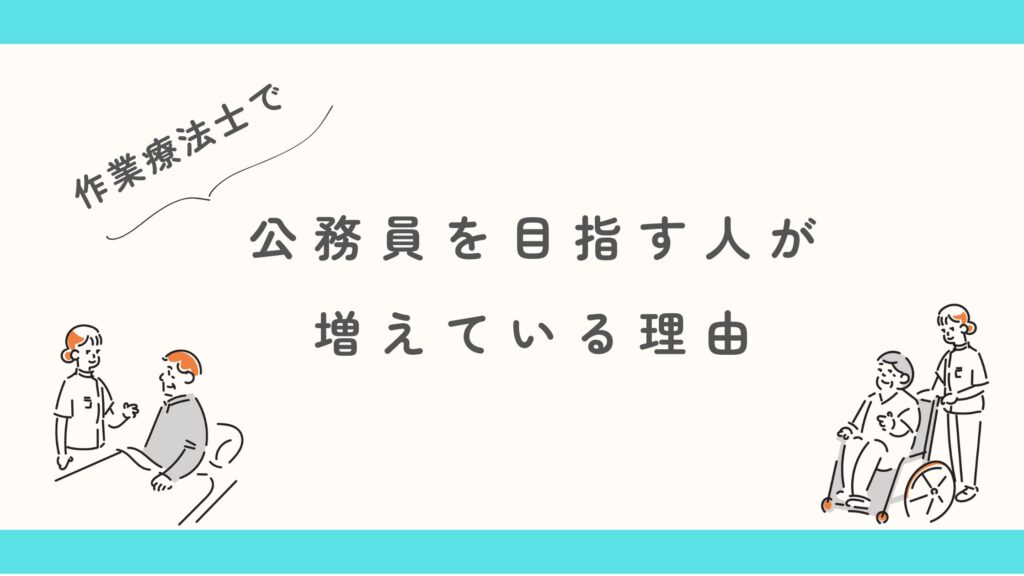
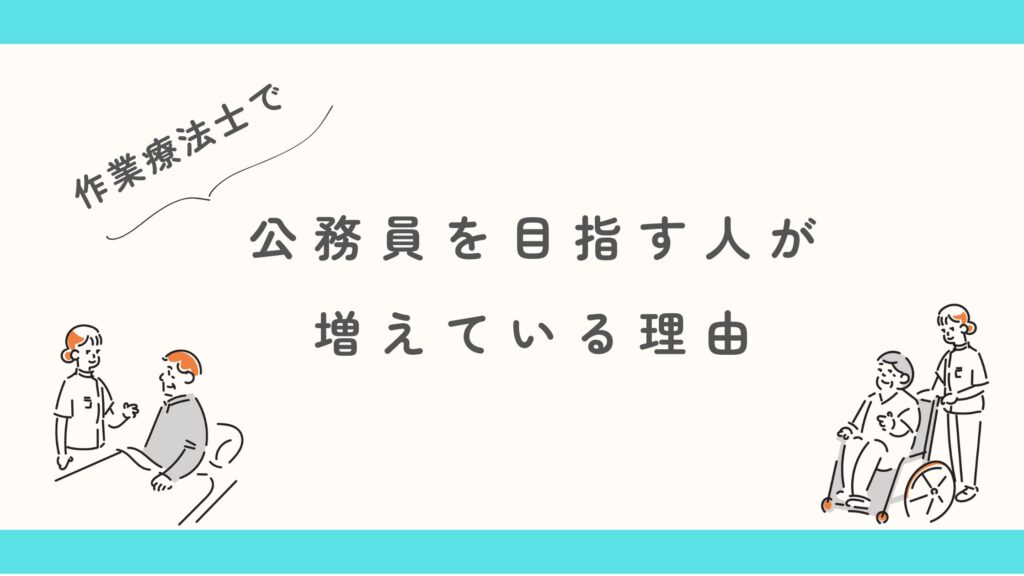
ここ数年、OTから「公務員を目指してみようと思っているんです」という相談を受けることが増えてきました。
臨床にやりがいを感じながらも、
働き方や将来に対する不安から“安定した道”を選びたくなる気持ちはごく自然なものです。
- 仕事と生活のバランスを重視したい
- 医療現場に限界を感じた人が多い
- 社会的信用や安定を求めている
ここでは、なぜ今、
OTがセカンドキャリアとして公務員を考えるのか、代表的な理由を3つ紹介します。
仕事と生活のバランスを重視したい
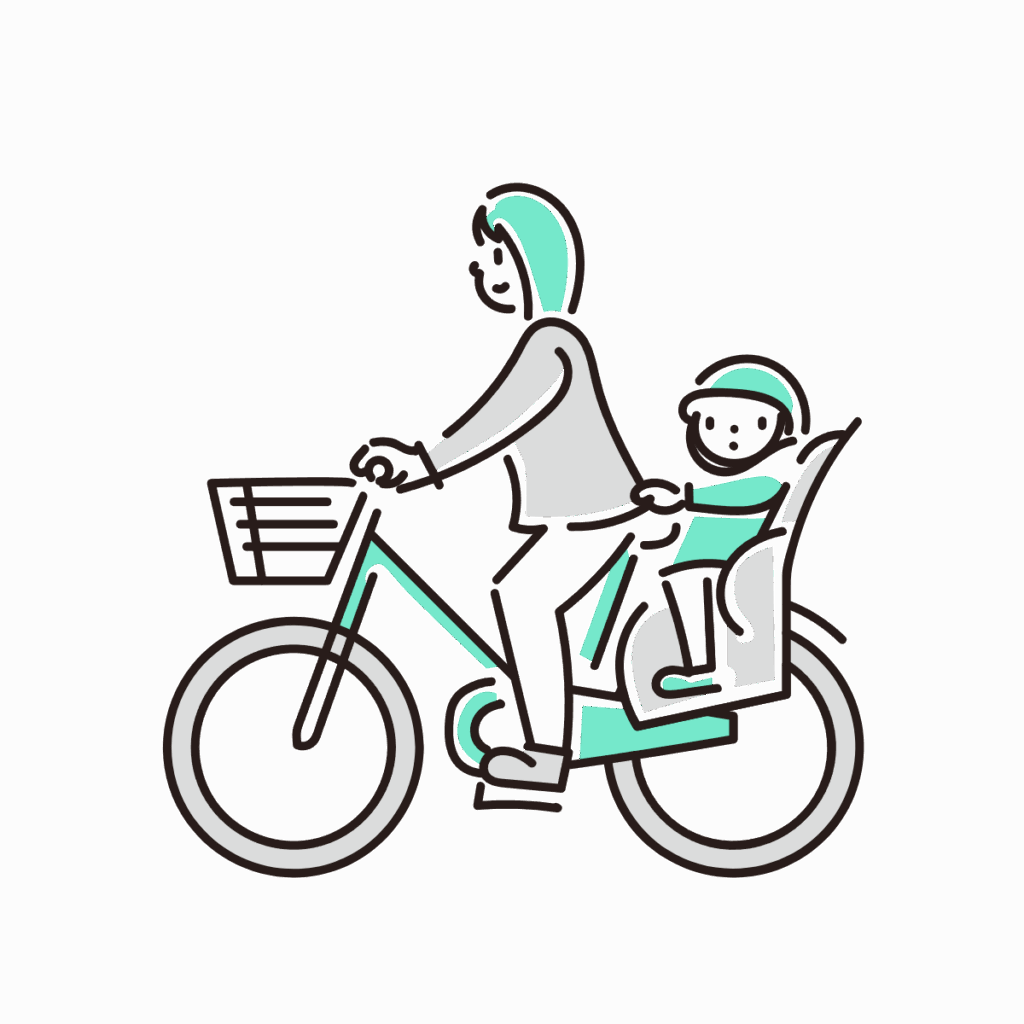
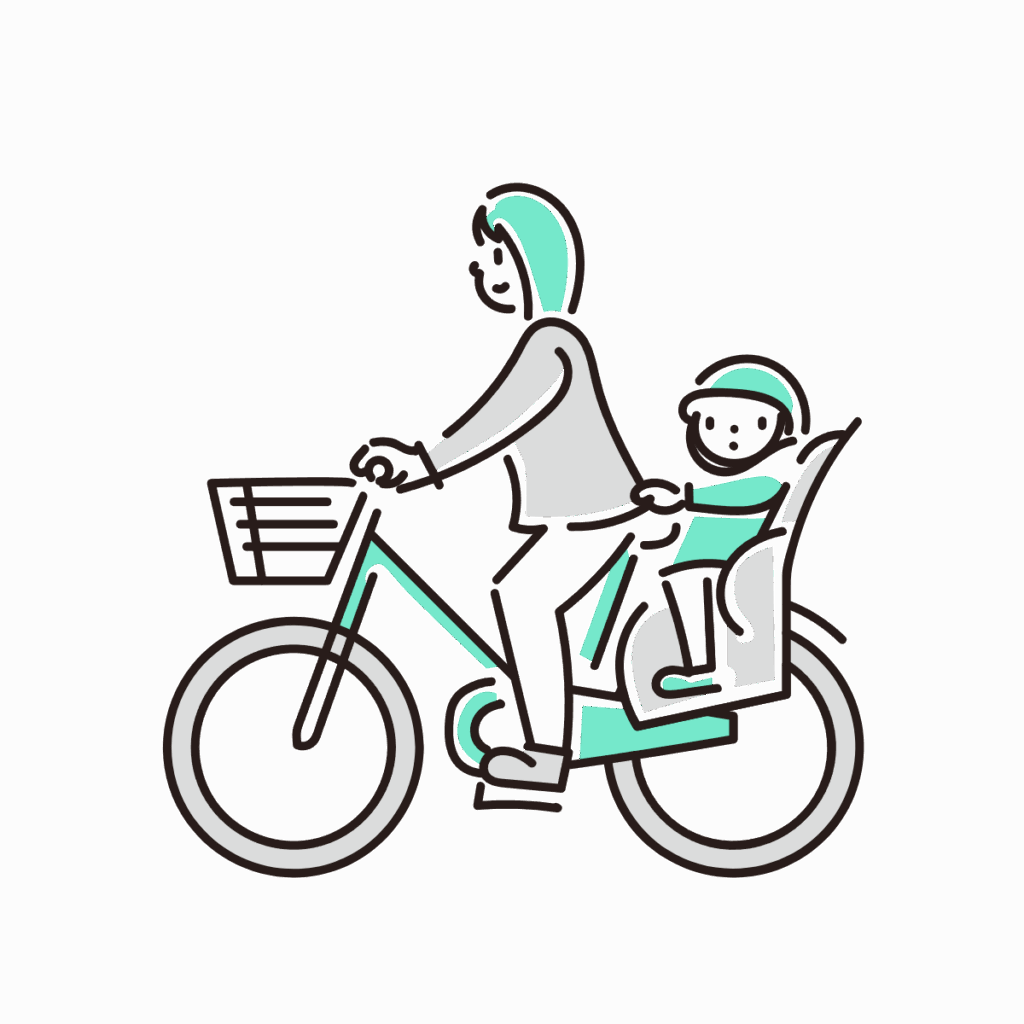
臨床現場では、時間に追われる日々が続きます。
とくに急性期や回復期の病院では、業務量も多く残業が日常的に発生することも。
- 「もっと家族との時間を大切にしたい」
- 「子育てや介護と両立できる働き方がしたい」
そんな思いを抱える作業療法士にとって、公務員は魅力的な選択肢となります。
なぜなら公務員は、
- 勤務時間がほぼ固定
- 原則として土日祝は休み
- 有給・産休・育休の取得率が高い
- ワークライフバランスを重視する職場が多い
といった特徴があるからです。
とくに女性OTや育児中のスタッフからは、
「時間的余裕のある職種に移りたい」という声が非常に多く聞かれます。
医療現場に限界を感じた人が多い
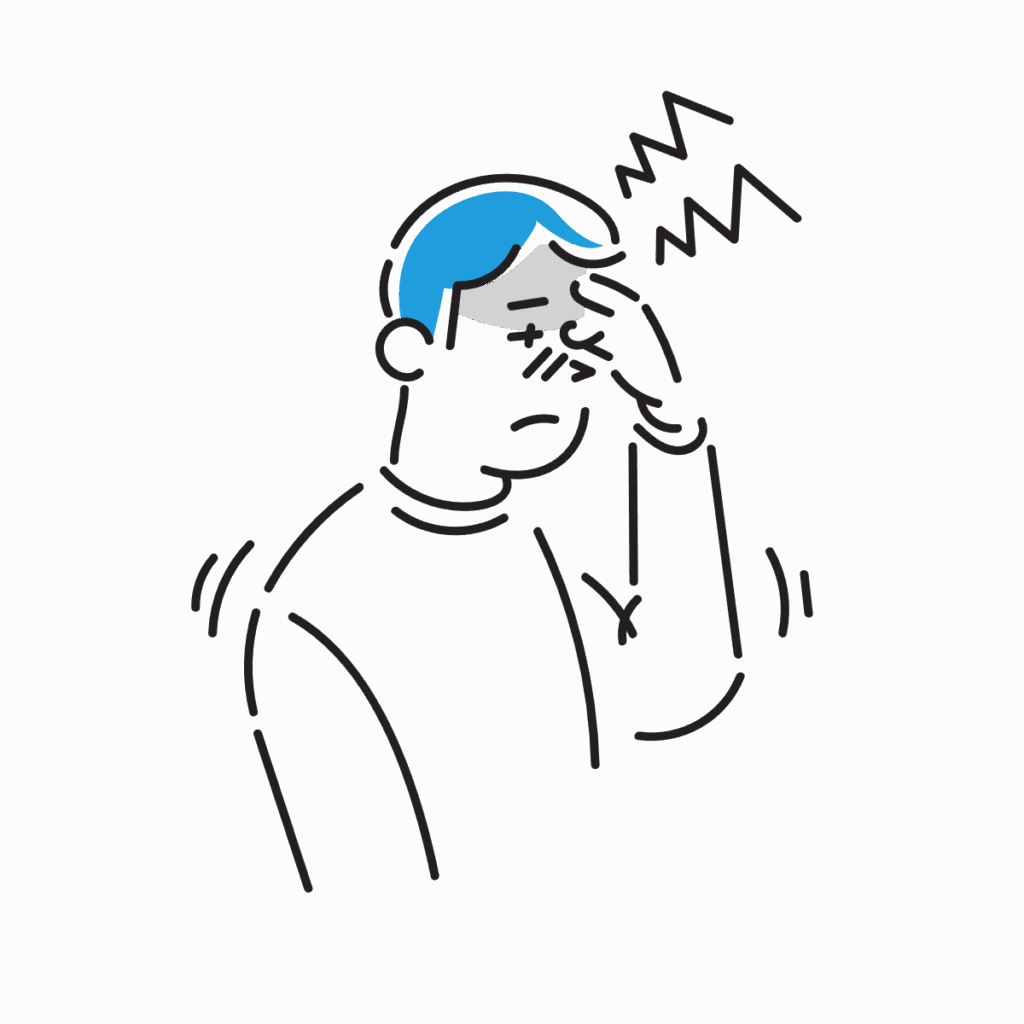
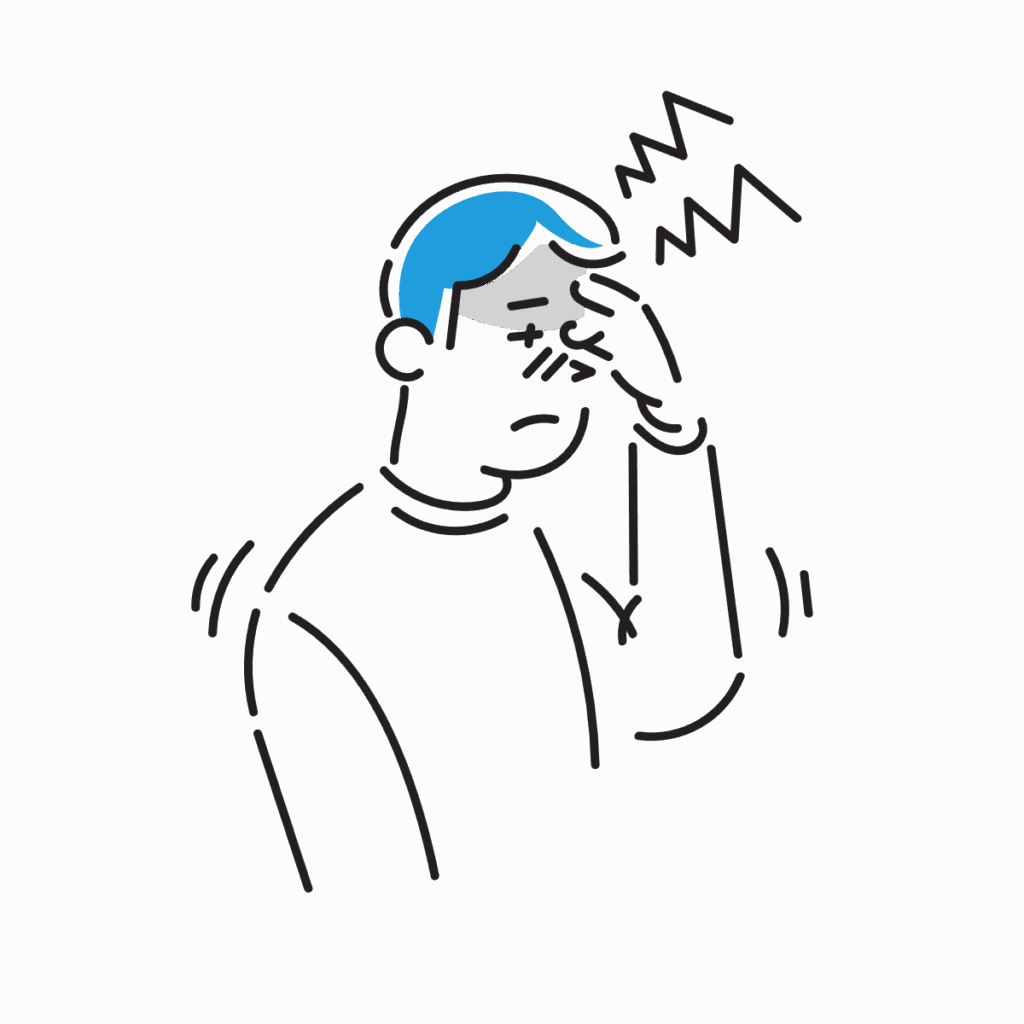
OTとして数年〜10年以上働いている方のなかには、
「臨床に限界を感じる」という理由で転職を検討するケースも増えています。
- 対象者との関わりがルーティン化してきた
- 経験が増えても給与や評価に反映されにくい
- チーム間の温度差にストレスを感じる
- 精神的に追い詰められてしまった
こうした“心の疲れ”は、どんなベテランOTにも起こり得ることです。
- 「同じ人を支援する仕事でも、もっと社会の仕組みや制度に関われる立場に行きたい」
- 「現場でのサポートよりも、行政の側から地域を支えたい」
そんなふうに考え始めたとき、
公務員というキャリアは“支援のかたちを変える”選択肢になり得ます。
社会的信用や安定を求めている


働くうえでの「安心感」や「信用」は、年齢を重ねるごとに大きな意味を持つようになります。
とくに、住宅ローン・教育資金・老後の備えなど、
将来のライフプランを真剣に考えるタイミングでは、
“公務員”という肩書きのもつ社会的安定性が強く意識されるようになります。
- 雇用が安定している
- 給与テーブルや昇給制度が明確
- 福利厚生・退職金・共済などが手厚い
- 社会的な信用が高く、転職後も評価されやすい
これらの理由から、
「作業療法士としての専門性を活かしつつ、長く安心して働ける場所を選びたい」
という思いで公務員を目指す方が増えています。
作業療法士が公務員になれる3つのルート
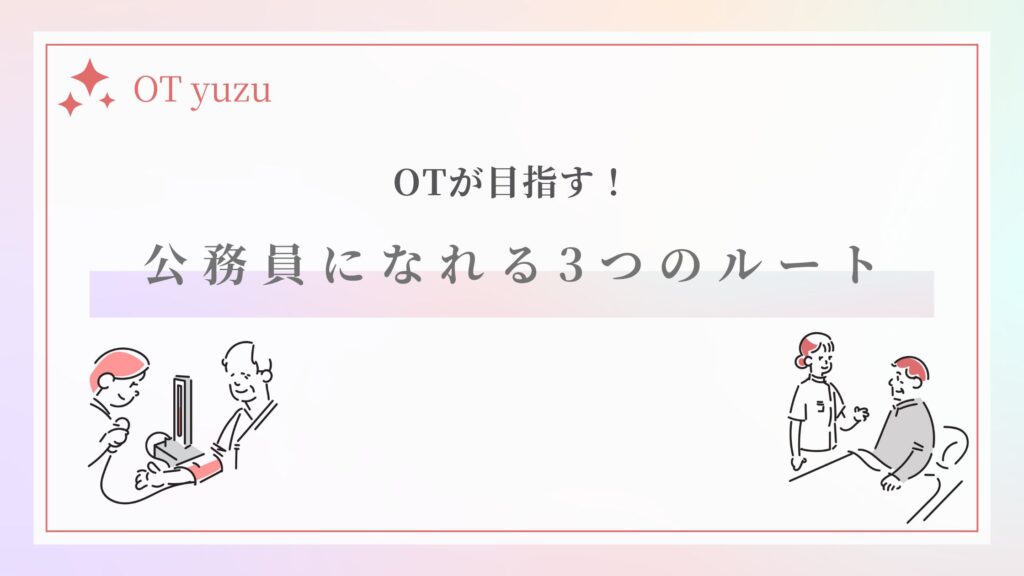
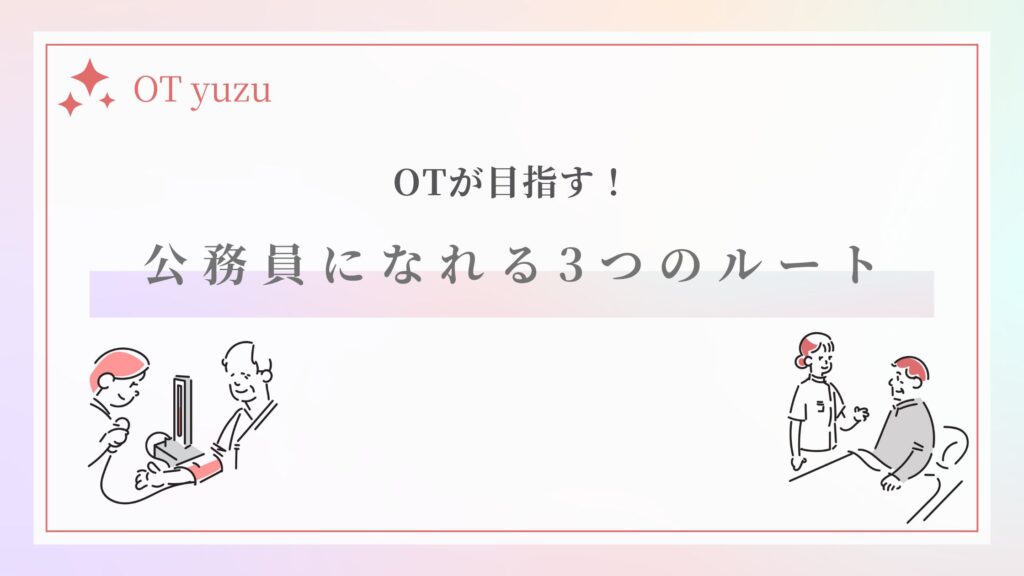
実は、OTとしての資格や経験を活かせる“公務員的ポジション”は意外に多く存在します。
ただし、一般的な行政職とは異なり、
“福祉系”や“医療系”の職種に特化したルートを狙うことがポイントです。
- 保健師・福祉職などの行政系ルート
- 地域包括支援センターなど相談職ルート
- 障害・教育・福祉支援などの現場系ルート
ここでは、作業療法士から目指せる代表的な3つの公務員ルートを紹介します。
保健師・福祉職などの行政系ルート


作業療法士が受験できる公務員試験のなかには、
「福祉職」「社会福祉士枠」「心理系職種」など、
医療福祉分野の専門性が問われる行政職が存在します。
このルートで採用されると、
- 高齢者・障害者福祉に関する行政相談
- 地域リハビリテーションの企画運営
- 健康施策の立案と評価(保健センター勤務など)
- 調査・統計・行政施策の実務
のような業務を担当します。
たとえば、
東京都や大阪府、政令指定都市では、「社会福祉職(資格不問/福祉系経験者歓迎)」という区分でOTの採用実績があります。
ポイントは、必ずしも「作業療法士」の名で募集されるわけではないこと。



そのため、試験要項を丁寧に読み込み、自分が該当するかを確認することが大切です。
地域包括支援センターなど相談職ルート
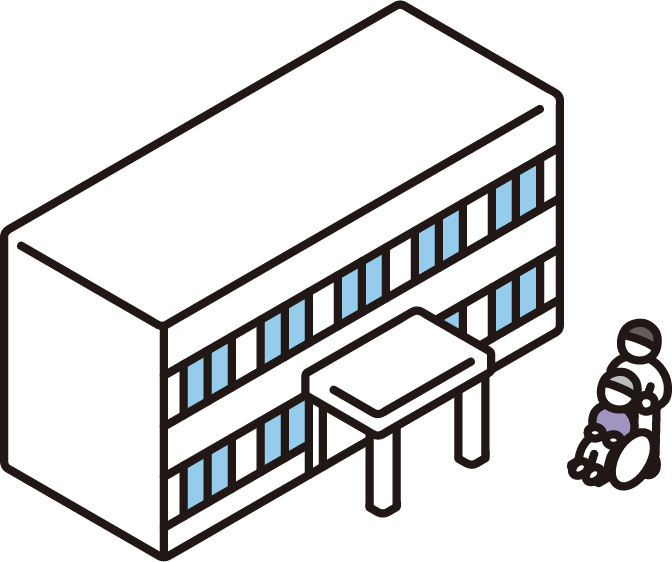
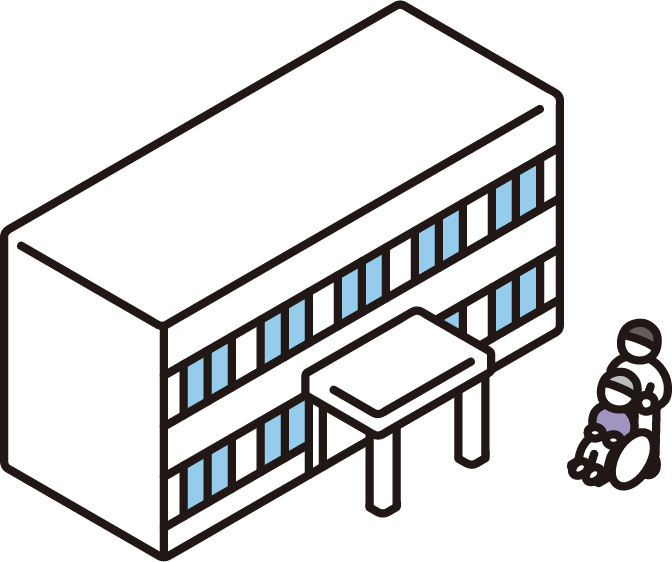
地域包括支援センターは、
高齢者の総合相談窓口として全国に設置されている行政機関です。
ここでは、保健師・社会福祉士・主任ケアマネに加え、OTやPTの配置も徐々に進んでいます。
OTとしての経験がある方は、
- 高齢者の生活支援・介護予防相談
- 自宅訪問によるアセスメント
- 地域の多職種連携・ネットワークづくり
- 支援計画の策定やモニタリング
のような業務で力を発揮できます。
特に、生活機能評価や福祉用具選定、住宅改修のアドバイスなどはOTの得意分野。



医療職としてのスキルが、そのまま地域支援に活かされる仕事です。
多くの自治体では委託職員(会計年度任用職員)や嘱託職員としての
雇用からスタートすることもありますが、継続的に勤務すれば、常勤採用や正規登用の道もあります。
障がい・教育・福祉支援などの現場系ルート


もう一つのルートが、直接支援型の公務員職です。
たとえば以下のようなケースがあります
| 分野 | 職場例 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 障がい福祉 | 療育センター・障がい者支援施設 | 発達支援・日常生活訓練・自立支援計画 |
| 教育 | 特別支援学校・通級指導教室 | 支援計画作成、生活支援、教員と連携 |
| 高齢者支援 | 市町村の福祉課・介護予防課 | 地域支援事業の立案・実行・モニタリング |
これらの現場では、「資格+現場経験」が非常に重宝されます。
特に、発達障害や認知症分野に詳しいOTは、
指導・研修・地域支援の分野で引き合いが強くなっています。



民間委託から始まり、行政直轄の職員へキャリアアップする人も少なくありません。
セカンドキャリアに公務員が選ばれる3つの理由
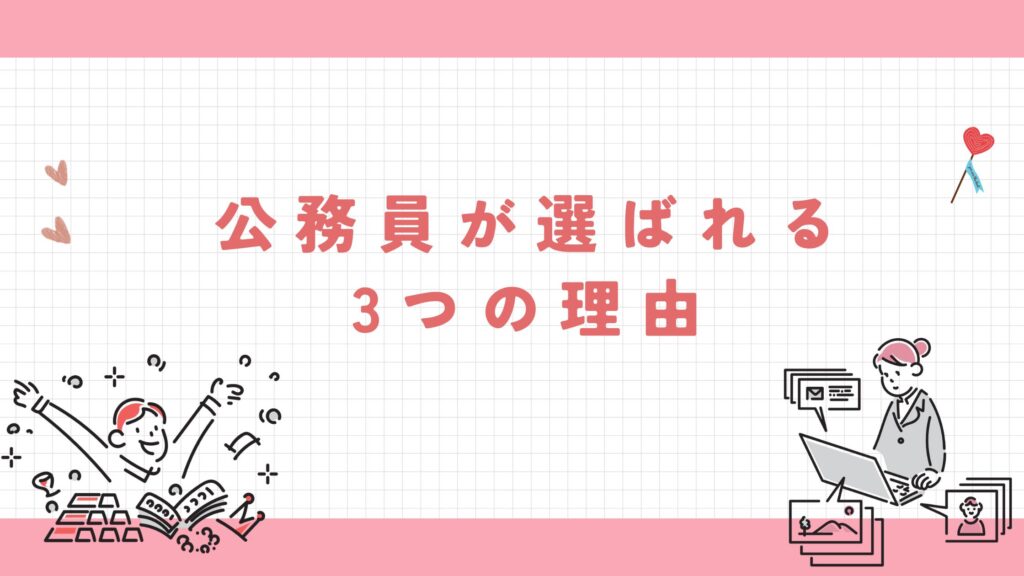
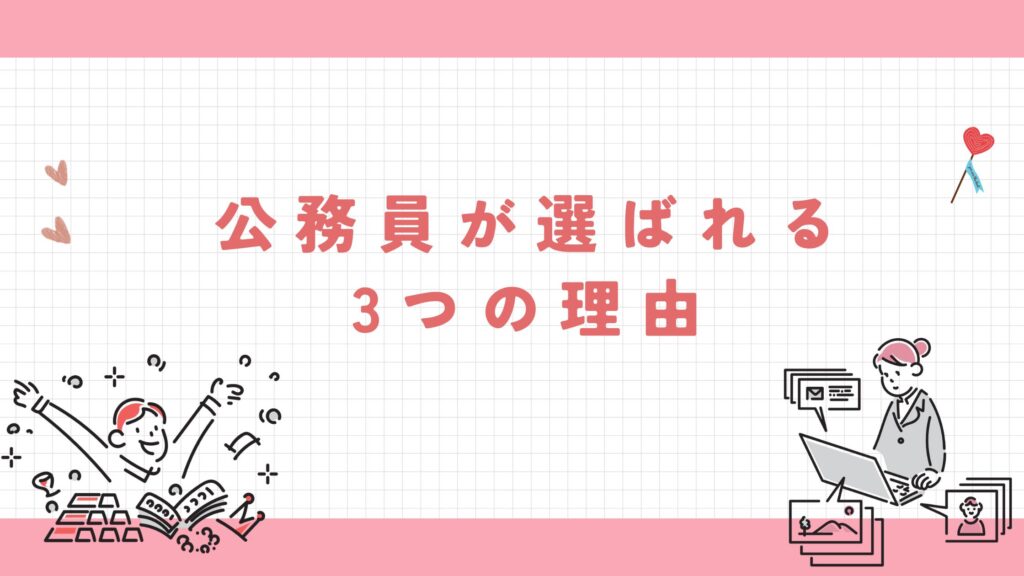
OTを辞めたあとに、公務員という選択肢が浮上する理由は、ただ安定しているからではありません。
それ以上に、作業療法士としての経験を活かしながら、
安心して長く働ける環境があることが、多くの人にとって魅力となっているのです。
- 安定した給与と待遇が魅力
- 定年まで働ける環境がある
- OTとしての経験が活かしやすい
ここでは、セカンドキャリアとして公務員が選ばれる理由を3つに絞って、具体的に解説します。
安定した給与と待遇が魅力
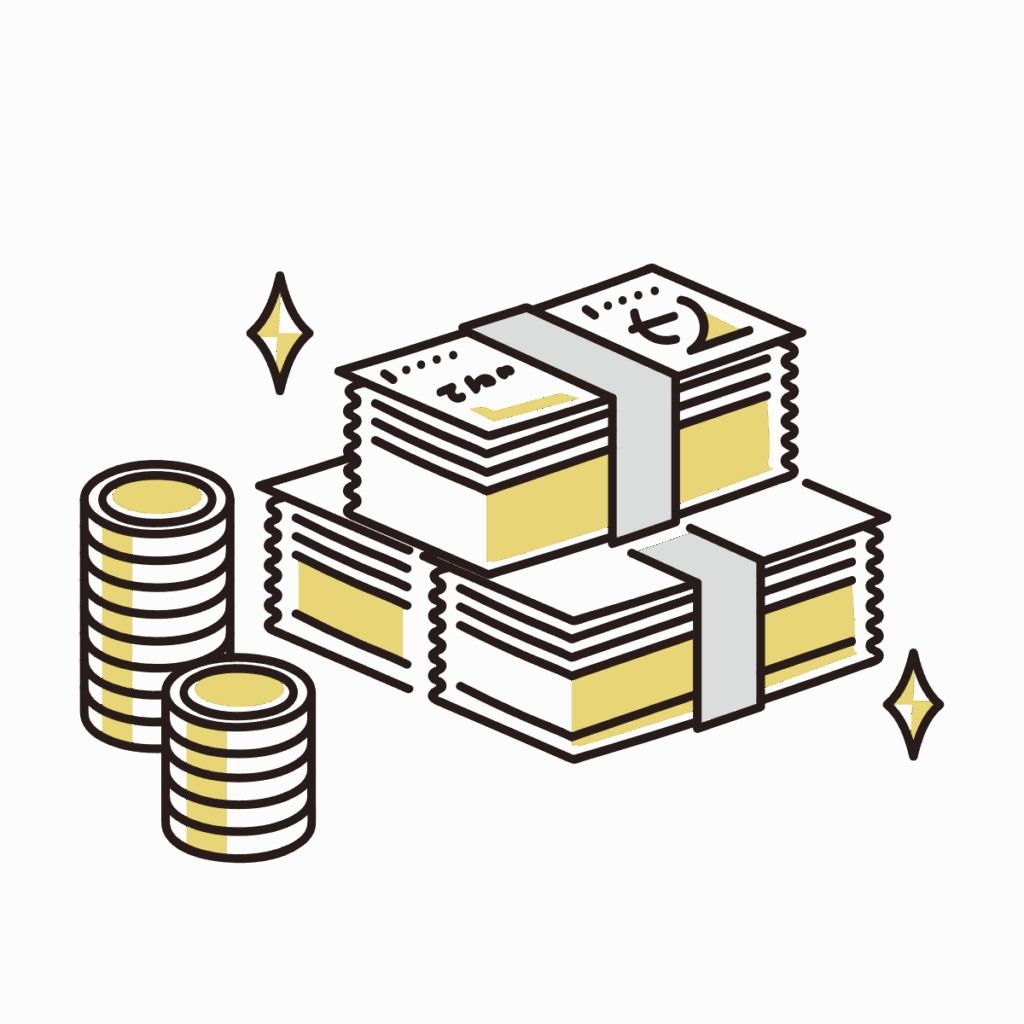
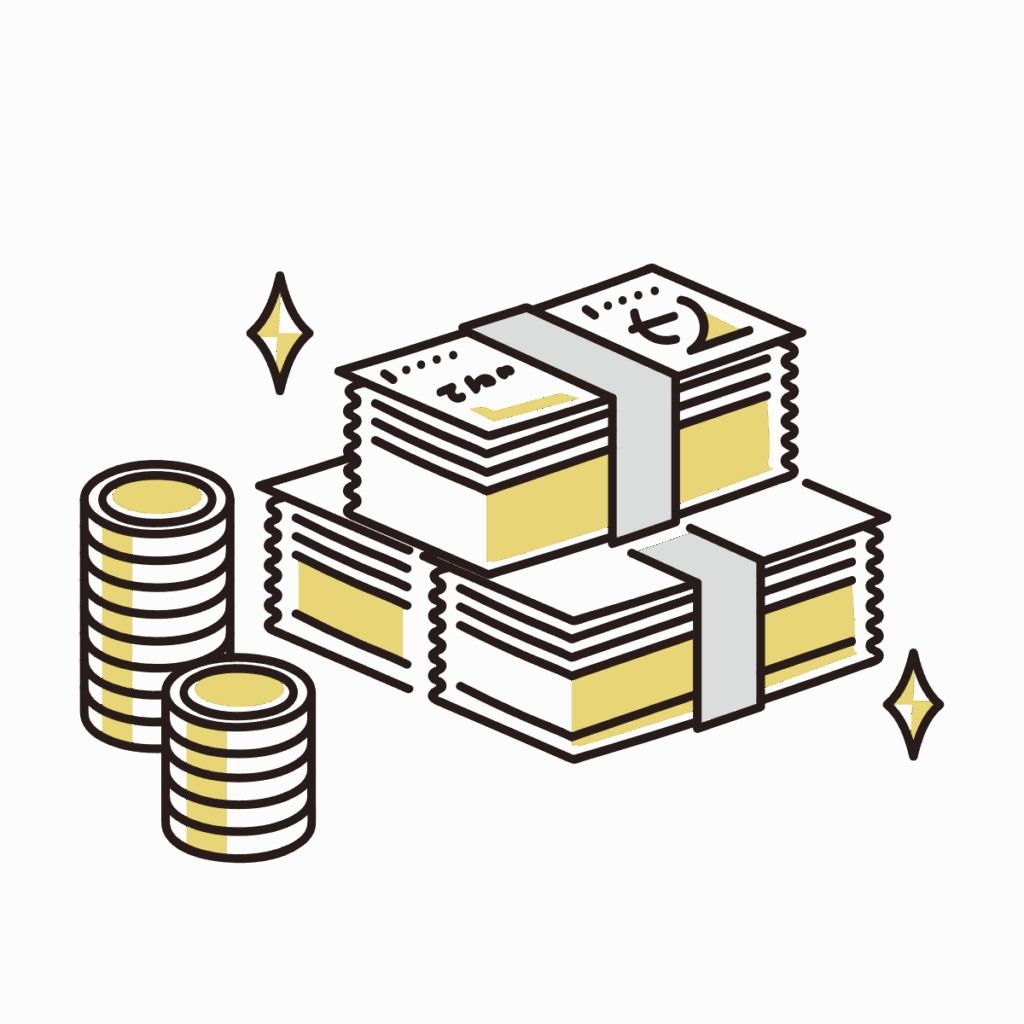
医療・介護の現場では、
経験年数を重ねても昇給がごくわずかだったり、
管理職になっても責任ばかりが増えて待遇が変わらないという声が多く聞かれます。
一方、公務員は給与体系が明確で、年齢・経験に応じた着実な昇給が見込める制度が整っています。
- 定期昇給が制度化されている
- 地方自治体ごとに賞与(期末・勤勉手当)が支給される
- 超過勤務手当、扶養手当、住居手当などが手厚い
- 定年再雇用や育児休業制度も明確化されている
また、福利厚生や年金制度も安定しており、
将来の生活設計が立てやすいことは、民間では得がたい安心材料です。
定年まで働ける環境がある


医療現場では、体力や感情労働の負担が大きく、
「このまま60代まで働けるのか?」と感じる人も多いはずです。
公務員の場合、
- 定年までの雇用継続が前提(原則65歳まで)
- 定年前後の雇用延長制度(再任用制度)も整備
- 長期勤務による年金や退職金への反映が大きい
- 突発的な異動や配置転換はあるが、極端なストレスは少ない
のような特徴があります。
- 「今後、子どもが大きくなる」
- 「住宅ローンを抱えている」
といった長期的なライフプランを持つ方にとって、
公務員の安定性は非常に大きな強みになります。
OTとしての経験が活かしやすい
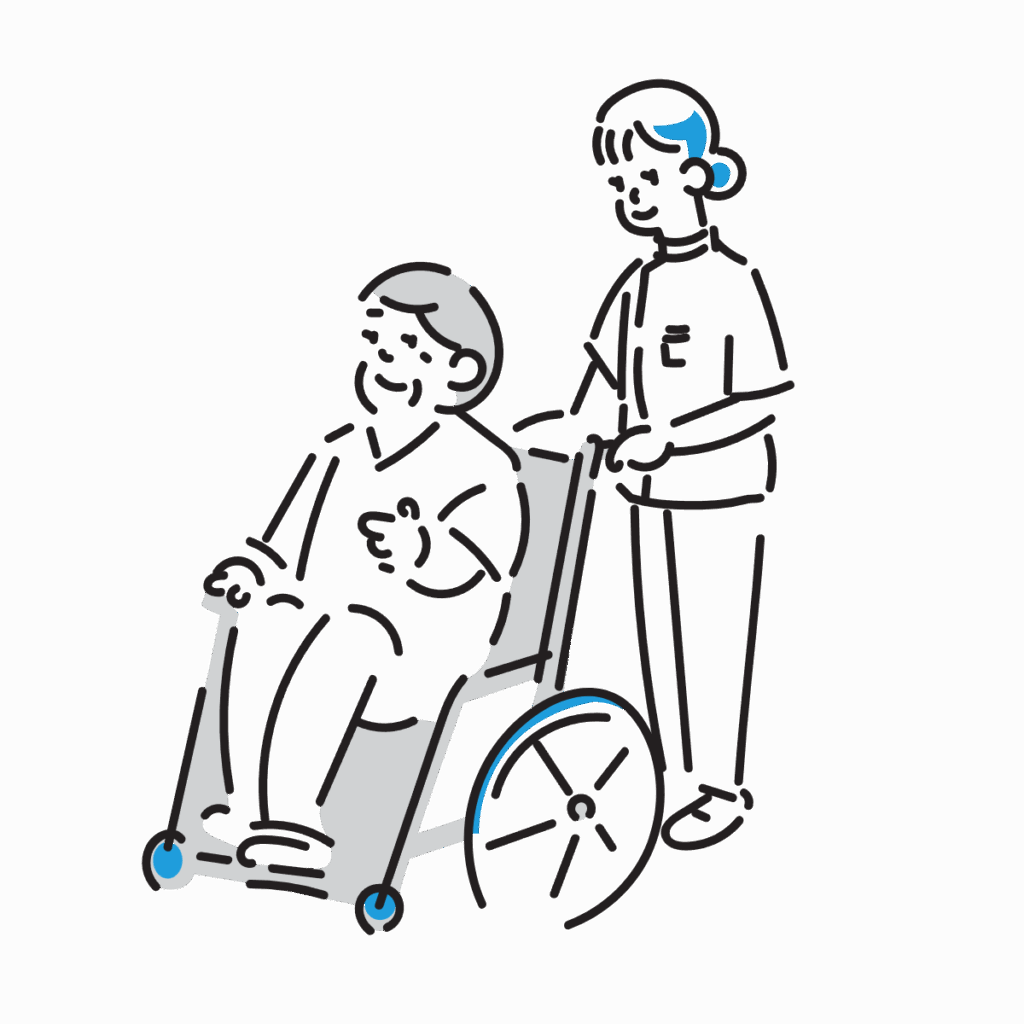
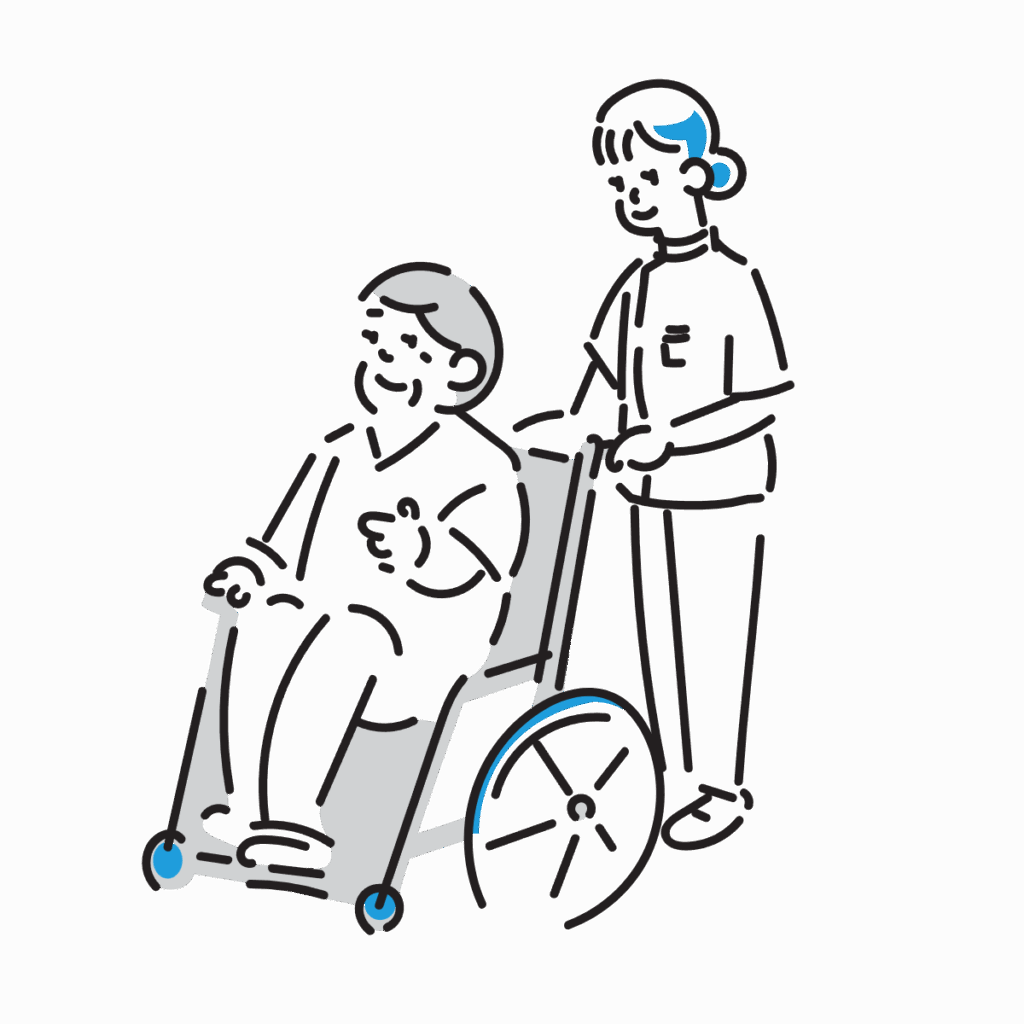



OTやめたら、すべてがリセットされるのでは?
という不安も多いですが、
実は、公務員の中でもOT経験が活かせる職場は多く存在します。
たとえば
- 地域包括支援センター生活機能評価やADL支援計画
- 障害福祉課障害者支援や環境調整のアドバイス
- 教育現場発達障害の理解と個別支援計画のサポート
- 保健センター健康増進施策の立案・生活指導
特に、
- 「評価と支援」
- 「多職種との連携」
- 「制度理解と実行」
など、OTが日々の業務で磨いてきたスキルは、
行政分野との親和性が非常に高いのです。
また、面接や業務内で「現場経験を行政にどう活かすか」が語れることは、他業種転職者にない強みとなります。
\その一歩が未来を変える/
OTに人気の転職サイト3選公務員転職に向いている作業療法士の特徴
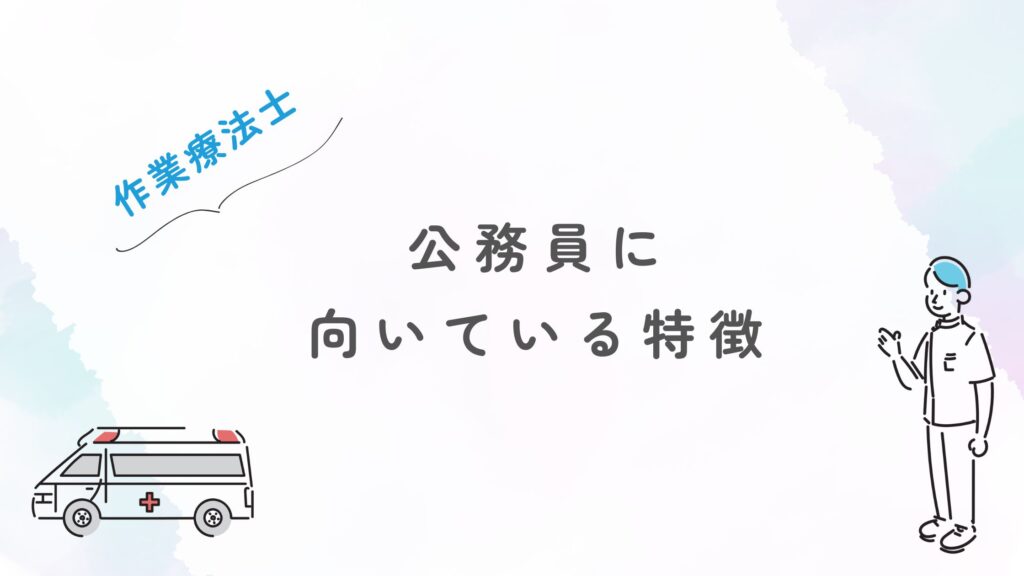
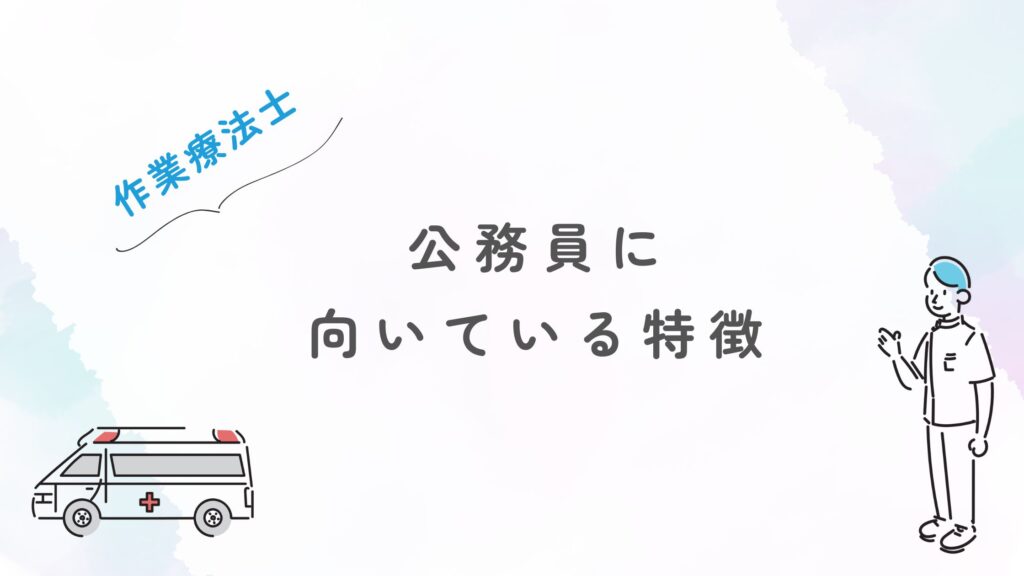
公務員という働き方は、誰にでも向いているわけではありません。
- チームでの連携や調整が得意な人
- 制度や計画に基づいて動ける人
- 現場から離れても支援したい人
作業療法士として働いてきた中でどんな人が公務員向きなのか、3つの特徴に分けて解説します。
チームでの連携や調整が得意な人


公務員の多くの職種では、関係機関との調整や多職種との連携が必須です。
これはまさに、作業療法士が普段の業務で自然と鍛えてきた力でもあります。
たとえば、
- 医師や看護師、PTとの連携を円滑に行える
- 家族との関係づくりや説明が得意
- ケースカンファレンスで要点を整理して話せる
このような人は、行政職における“調整役”として重宝されることが多いです。
特に地域包括支援センターや障害福祉部門では、
さまざまな職種との橋渡し役が求められるため、
現場で「調整役タイプ」だった人は、強みをそのまま活かしやすいでしょう。
制度や計画に基づいて動ける人
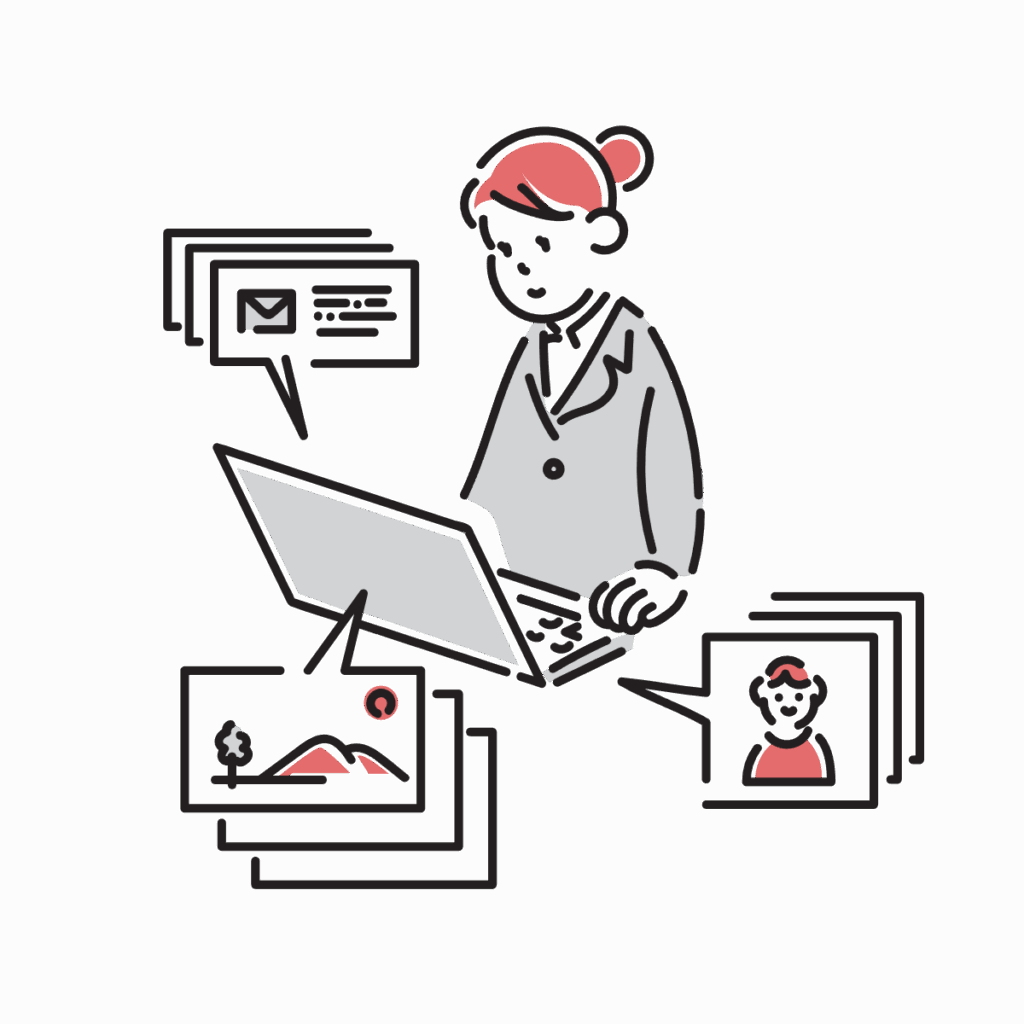
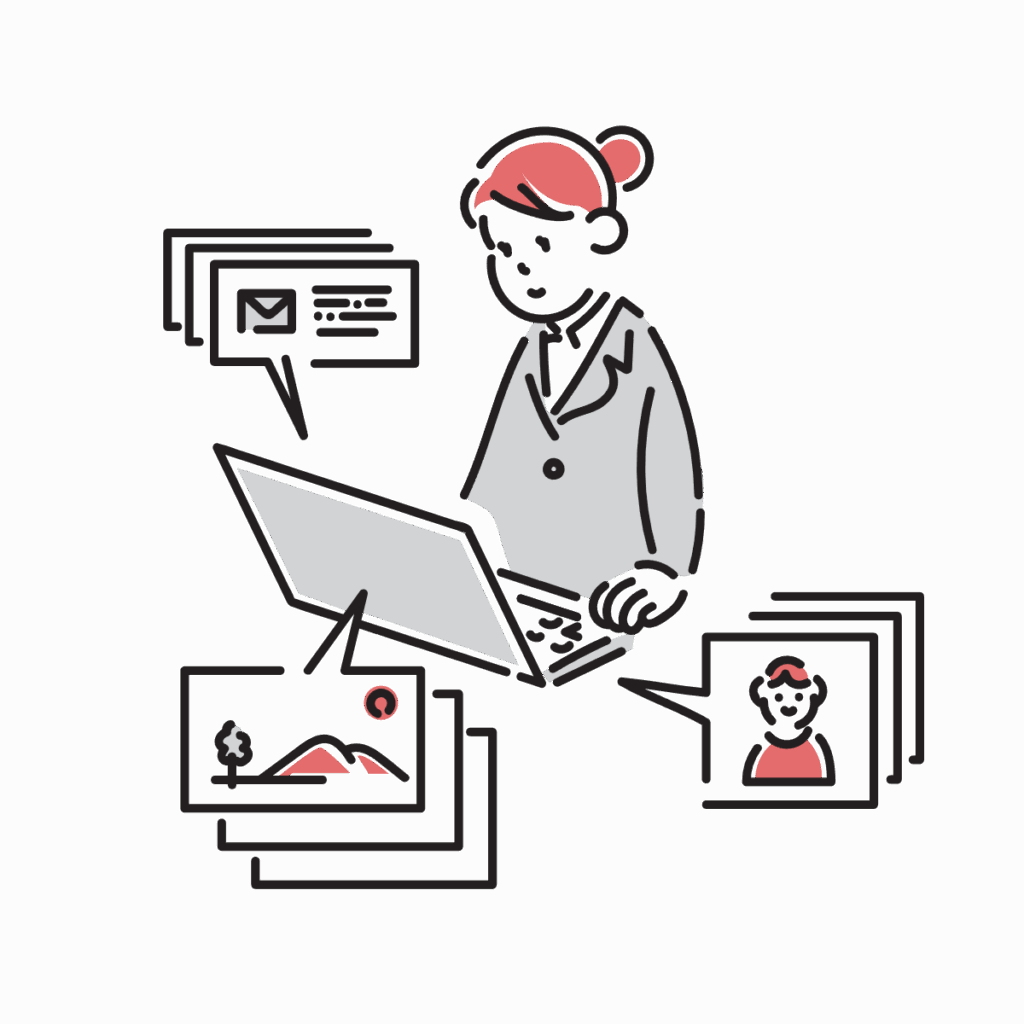
作業療法士の仕事は“臨機応変さ”が求められる一方で、
評価・記録管理・診療報酬など、
決められた手順や制度に基づいて仕事を進める側面も多く含まれています。
- 自立支援に必要な計画を立てる
- ケアマネと連携しモニタリングを行う
- 加算要件やルールを遵守する書類作成
このような業務を「苦じゃない」「むしろ得意」と感じる方は、公務員の環境にフィットしやすいタイプです。
特に行政職では、



自由なアイデアよりも“制度に忠実で正確な実行力”が評価されやすい傾向があります。
現場から離れても支援したい人


臨床から一歩離れることに不安を感じる方も多いですが、
「支援したい」という想いがあるなら、その形を変えるだけで十分活躍できます。
たとえば
- 地域リハビリの普及活動
- 高齢者の虐待防止支援
- 障害者の就労サポート事業
- 地域資源マップの作成や周知活動
これらは全て、OTとしての視点が求められる支援です。
むしろ、
“制度を動かす側の支援”という次のステージに進むチャンスとも言えます。
公務員転職の注意点と準備すべきこと
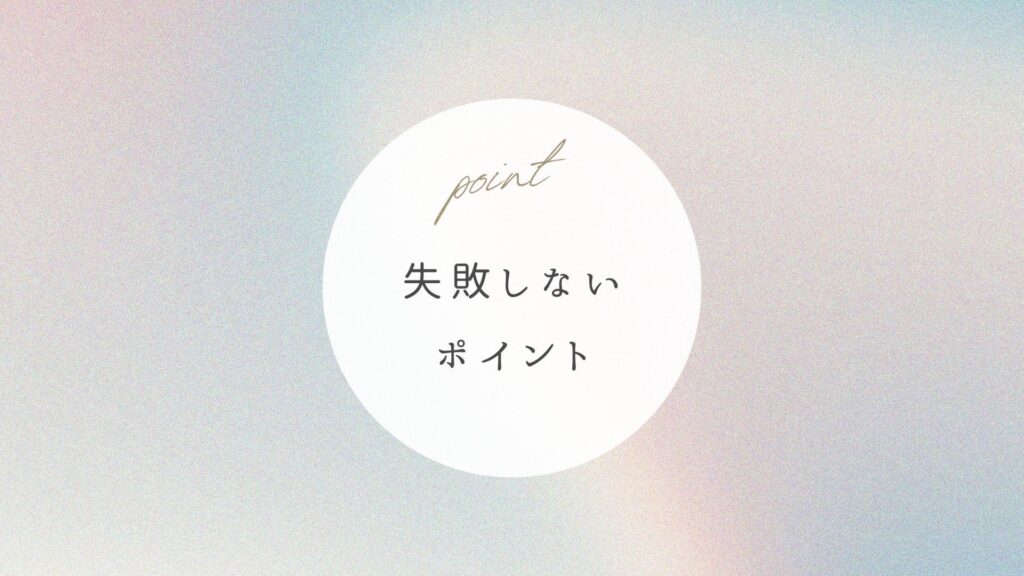
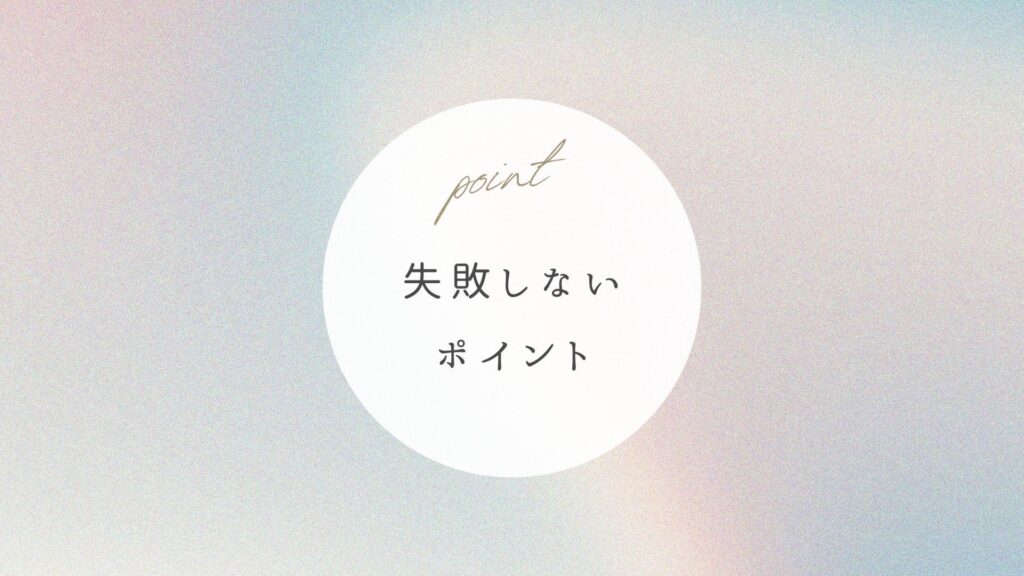
「作業療法士としての経験を活かして公務員へ」
そう考えたとき、希望と同時に不安も浮かんでくるのが自然です。
現実には、公務員特有の試験制度や採用条件、職場文化など、事前に知っておくべきポイントがいくつかあります。
- 筆記試験と倍率の壁
- OTから離れる覚悟が必要な場合も
- 事前の情報収集と職種選びが重要
ここでは、押さえておくべき注意点と、今からできる準備について解説します。
筆記試験と倍率の壁
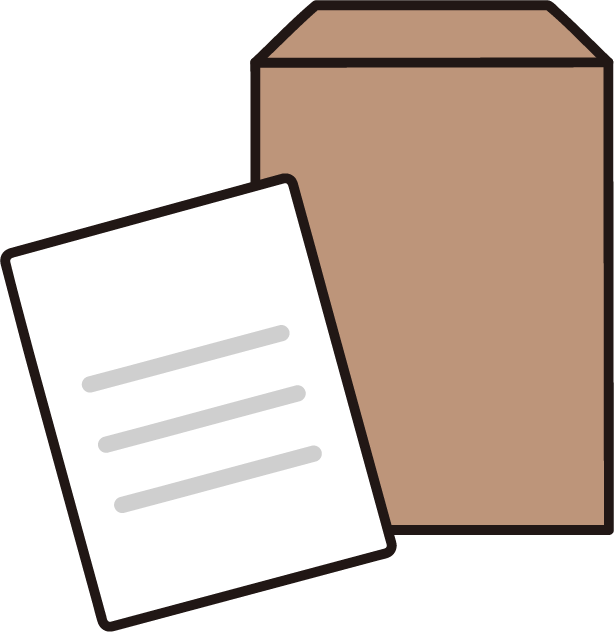
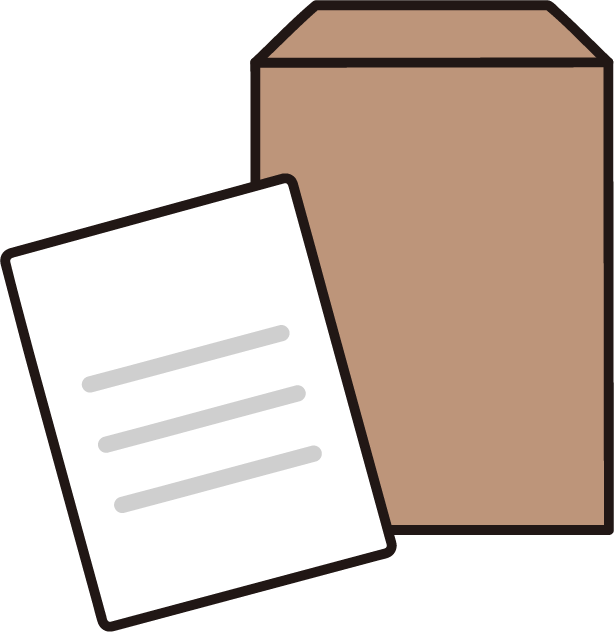
公務員転職で避けて通れないのが、筆記試験の存在です。
とくに地方公務員では、
教養試験(一般知識・文章理解・数的推理)や論作文、面接が課されることが一般的です。
- 年齢制限(多くは35歳以下)がある職種も
- 試験倍率が10倍以上になる自治体もある
- 勉強に数ヶ月〜半年かかることも想定しておく必要がある
また、社会福祉職や相談支援職でも、
法律・制度の知識や、ケーススタディを問う問題が出題されます。
そのため、「受かるか不安」と感じる方は、



非常勤や会計年度任用職員から経験を積むのも現実的な選択肢です。
OTから離れる覚悟が必要な場合も


作業療法士としての資格や経験が活かせるとはいえ、
臨床的なリハビリ業務を完全に離れるケースが多いのも事実です。
- 医療行為は一切ない
- 利用者とは間接的な支援が中心
- 書類作業や制度対応が日常業務の多くを占める
そのため、「人と直接関わって支援したい」という思いが強い方には、
物足りなさや違和感を感じる可能性もあります。
大切なのは、
事前の情報収集と職種選びが重要


公務員と一口に言っても、その職種や業務内容は非常に多岐にわたります。
そのため、
希望する自治体や機関の募集要項を丁寧に読み込むことが最も重要です。
チェックすべきポイント
- 応募条件(資格・年齢・実務経験)
- 試験日程と内容
- 配属部署の具体的な業務内容
- 勤務形態(常勤・非常勤・嘱託など)
- 年収や福利厚生の詳細
また、転職サイトや自治体のキャリア相談、前例者の声を活用して、
なるべく具体的なイメージを持つようにしましょう。
実際に公務員転職をしたOTの体験談や、
セミナー・説明会に参加することで、「本当に自分に合っているのか」を確かめるヒントが得られます。
まとめ|作業療法士のセカンドキャリアに公務員という選択肢
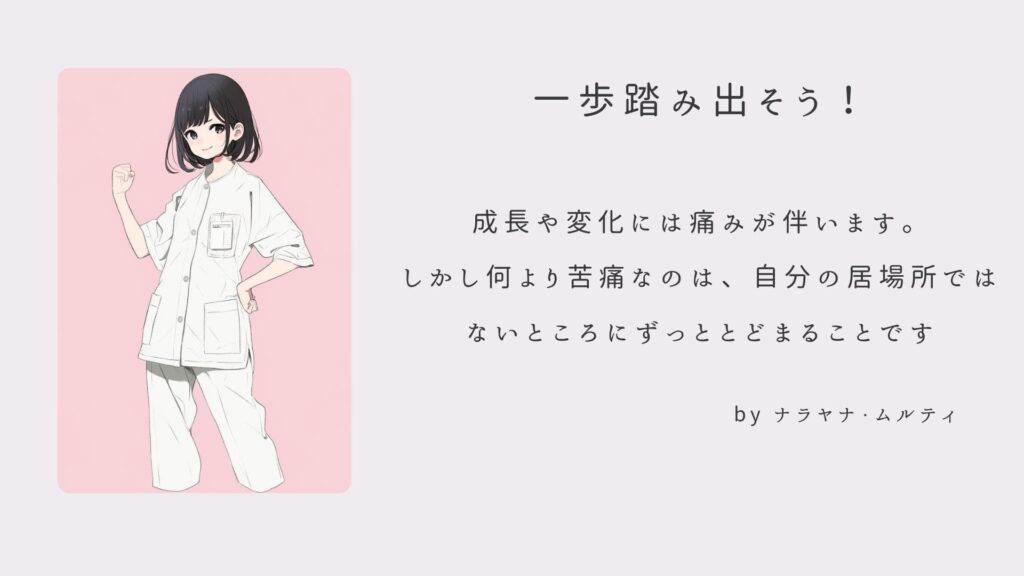
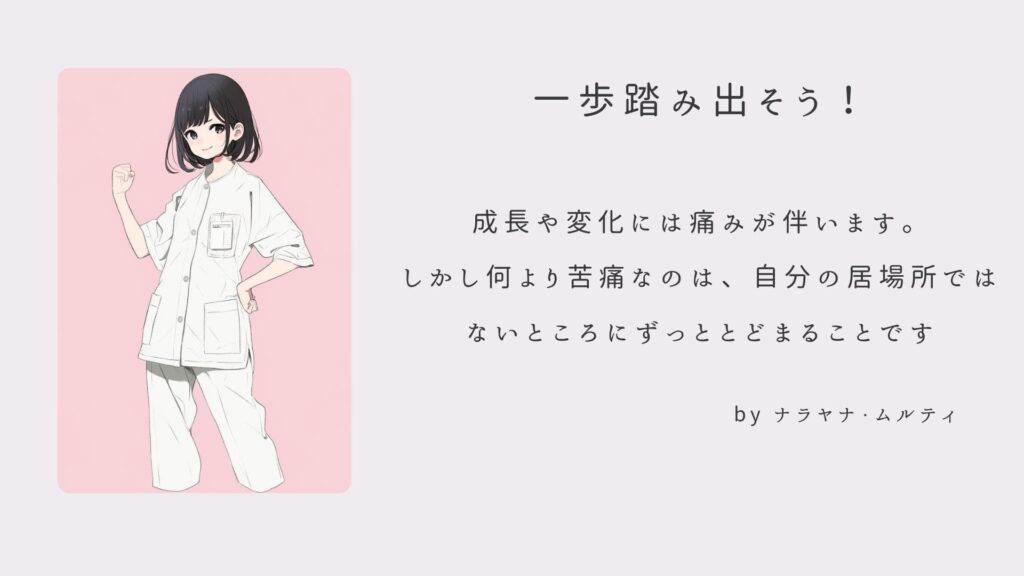
作業療法士として働きながら、公務員という安定したセカンドキャリアを考える人が増えています。
現場に限界を感じたり、将来の働き方に不安を抱えたりするのは、特別なことではありません。
公務員の仕事には、
OTとしての経験を活かせる場面が多くあり、
制度設計や地域支援といった「新たなかたちの支援」が求められています。
とはいえ、試験や仕事内容のギャップもあるため、事前の情報収集と自己分析が欠かせません。
- 「どう生きたいか」
- 「どんな価値を届けたいか」
をベースに、次の一歩を考えてみてください。



公務員転職に限らず、セカンドキャリア全体の視野を広げたい方は、リハビリ専門の転職支援サイトで相談してみるのもおすすめです。