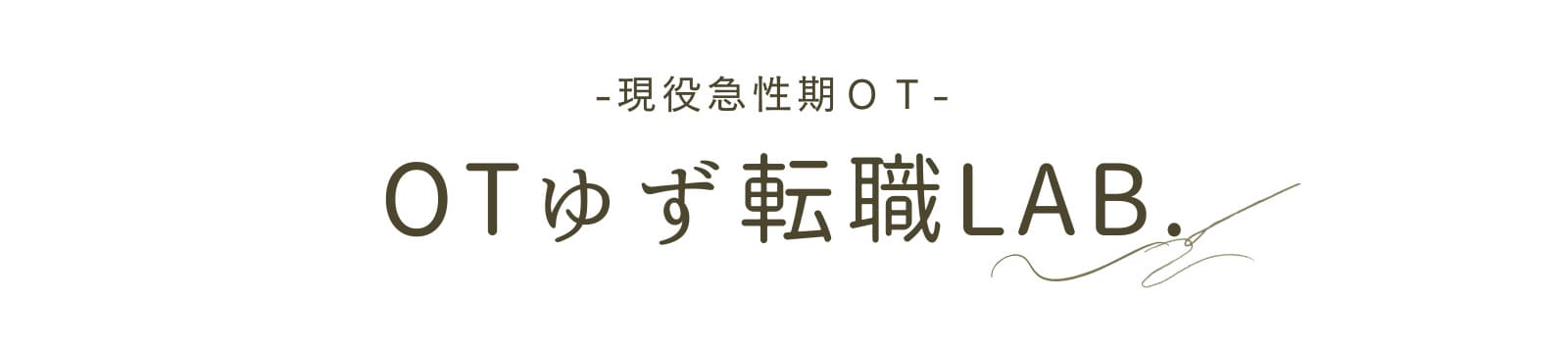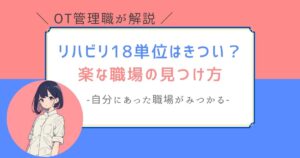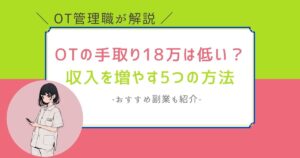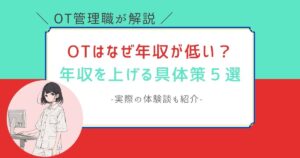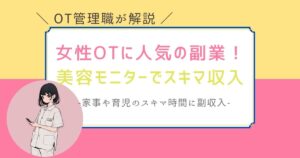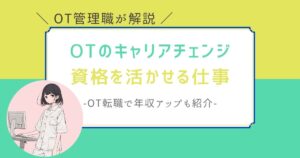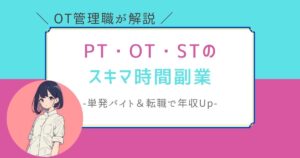急性期の現場で経験を積んだ作業療法士の中には、
 急性期OT
急性期OTこのままずっと急性期で働き続けるべきか?
と悩み始める方も少なくありません。
体力的な負担、働き方の見直し、患者との関わり方
理由はさまざまですが、次のステップとしてどの分野に進むべきか迷うのが本音ではないでしょうか?
本記事では、回復期・訪問リハ・維持期(老健・特養・デイケア)・精神科の4分野を徹底比較。
それぞれの特徴、メリット・デメリット、向いている人の傾向をわかりやすく解説しています。



あなたの経験や志向にマッチした転職先を見つけるヒントとして、ぜひ参考にしてください。


- OT歴15年以上、急性期OT
- 役職名は、係長
- 転職歴2回
- 回復期→在宅→急性期(現在)
- 2回の転職で年収250万Up
- 面接対策・転職ノウハウを発信
- (@yuzu_ot_reha)
急性期から転職を考える作業療法士が抱える悩みとは?
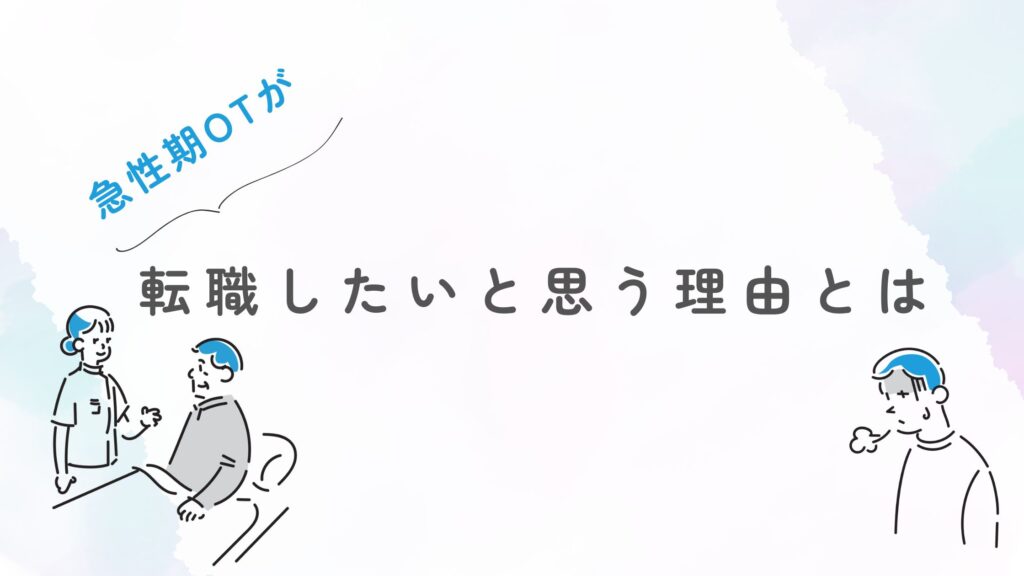
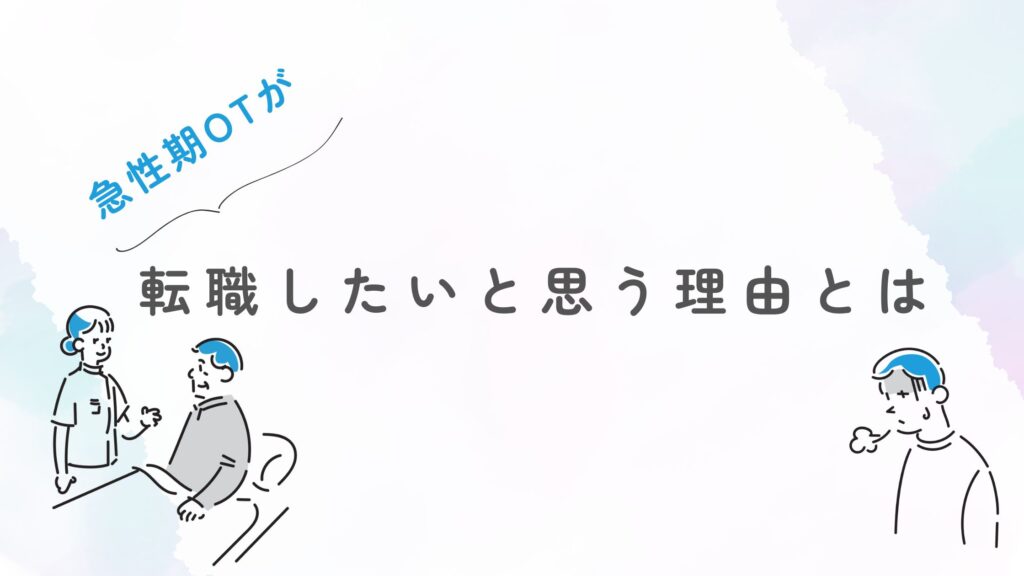
急性期の現場は、作業療法士として多くの経験とスキルを積める場所です。
一方で、日々の業務に追われる中で、
「このままの働き方を続けていいのだろうか」と悩み始める方も少なくありません。
- 急性期のやりがいと限界
- 体力的・精神的負担を感じやすい
- 今後のキャリアを見据えた不安
ここでは、急性期で働くOTが転職を考える背景にある代表的な悩みを3つの視点から整理します。
急性期のやりがいと限界
急性期では、入院直後の重症患者に対する関わりが中心となり、
医師や看護師と連携しながら迅速な判断と対応が求められます。
その分、「回復の瞬間に立ち会えるやりがい」が大きな魅力です。
しかし、
- もっと患者とじっくり関わりたい
- 退院後の生活まで関与したい
といった思いが強くなり、
急性期の限られた関与時間や制度の枠組みに、物足りなさや歯がゆさを感じることもあるのです。
体力的・精神的負担を感じやすい
急性期ではリハビリ提供時間に制限があるため、
1日のスケジュールが分刻みで動くような忙しさがあります。
特に以下のような負担を感じる方が多いです。
- 多数の患者を短時間で診なければならない
- 書類・カンファレンスなどの業務も膨大
- 担当変更や病棟異動も頻繁で落ち着きにくい
「体力的に限界を感じている」「ミスが怖くて気が休まらない」など、
心身の負担を理由に別の分野へ転職を考えるケースも少なくありません。
今後のキャリアを見据えた不安
急性期はスキルアップには最適ですが、長く働き続ける将来像が描きづらいと感じる方も多いです。
- 管理職よりも臨床を続けたいが選択肢が少ない
- 家庭やプライベートとの両立が難しい
こうした不安は、働き方や価値観の変化によって顕在化しやすくなります。



特に30代以降、「生活とのバランス」や「やりがいの再確認」を重視する傾向が強まります。
\あなたに合った職場が見つかる/
OTに人気の転職サイト3選急性期から回復期へのOT転職
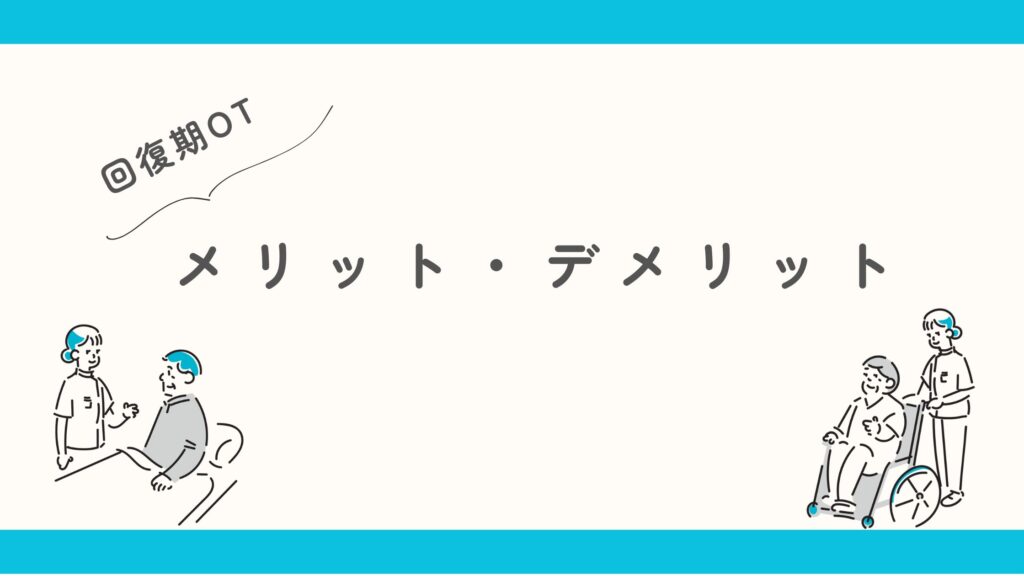
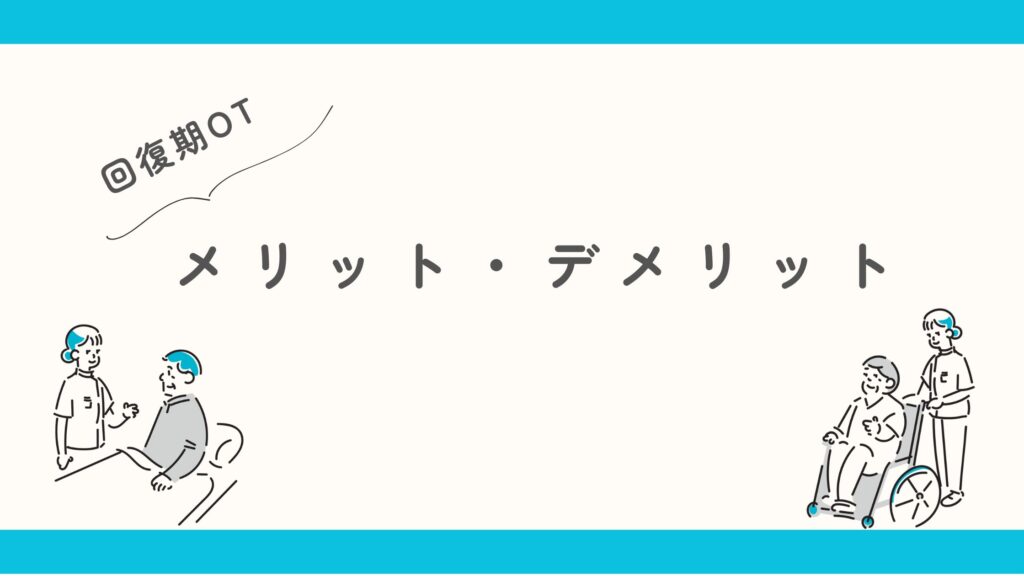
回復期は、急性期直後のリハビリを専門的に行うステージです。
作業療法士としての専門性を活かしながら、
患者とじっくり向き合える環境に魅力を感じる方も多いでしょう。
ここでは、急性期から回復期へ転職する際の代表的なメリットとデメリットを整理します。
メリット①:医療の流れを理解しやすく即戦力になれる
急性期で働いた経験があるOTにとって、
回復期は「次の段階」として非常になじみやすいフィールドです。
疾患の経過やリスク管理に関する知識が活かしやすく、初日から戦力として活躍できる場面が多くあります。
- 急性期で培った評価・対応スキルがそのまま活用できる
- 退院支援・生活復帰への橋渡しにやりがいを感じやすい
- 医師・看護師との連携もスムーズに取りやすい
「急性期と同じ医療チームに所属しながら、じっくり介入できる」ことに価値を感じる方も多いです。
メリット②:リハビリ計画を長期的に組みやすい
急性期では1日単位の短期目標が中心ですが、
回復期では1〜3ヶ月程度の入院期間を前提に、中長期の計画を立てられる点が魅力です。
- 評価→アプローチ→再評価のPDCAをしっかり回せる
- 食事・更衣・家事などADL訓練にしっかり取り組める
- 退院後の生活像を見据えた指導ができる
患者の「できた」「戻れた」という成果を実感しやすいため、



支援の達成感が得られやすいのも特徴です。
デメリット①:多忙で時間に追われがち
回復期も急性期に劣らず多忙で、
リハビリ単位を消化しながら業務をこなす日々になることも多いです。
- 複数患者のスケジュール管理が難しい
- 計画書・記録・会議などの間接業務が多い
- 他職種との連携に時間を取られがち
「じっくり関われると思っていたのに、実際はバタバタしていた…」と感じる方もいます。
デメリット②:急性期との差を感じないことも
医療機関によっては、
回復期でもリハビリ単位の効率や退院目標が重視されすぎている場合もあります。
- もっと生活期寄りかと思ったのに、急性期と変わらない
- 短期集中すぎて、じっくり関わる余裕がない
こうしたギャップを感じないためにも、事前に職場のリアルを確認することが大切です。


急性期から訪問リハへのOT転職
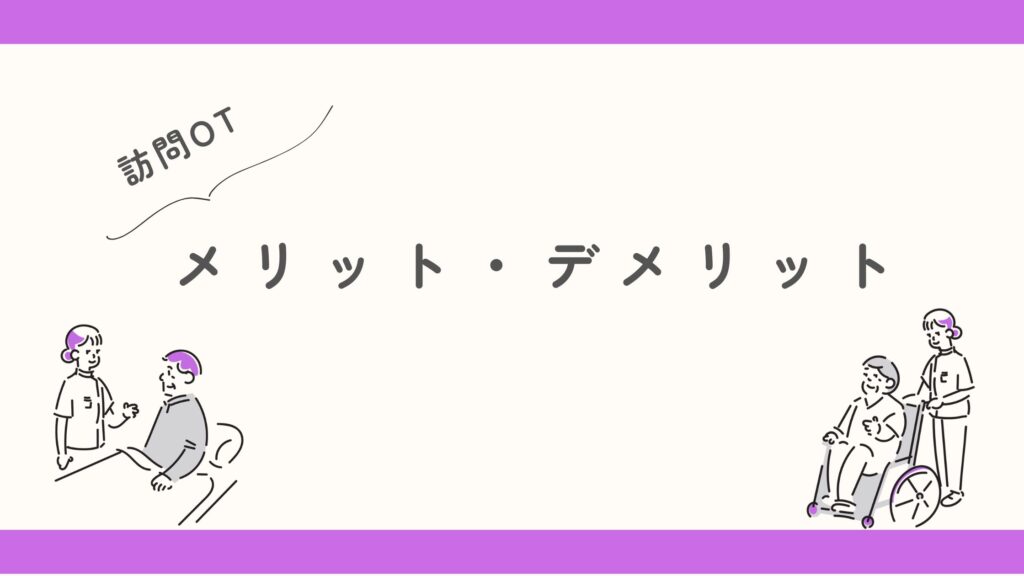
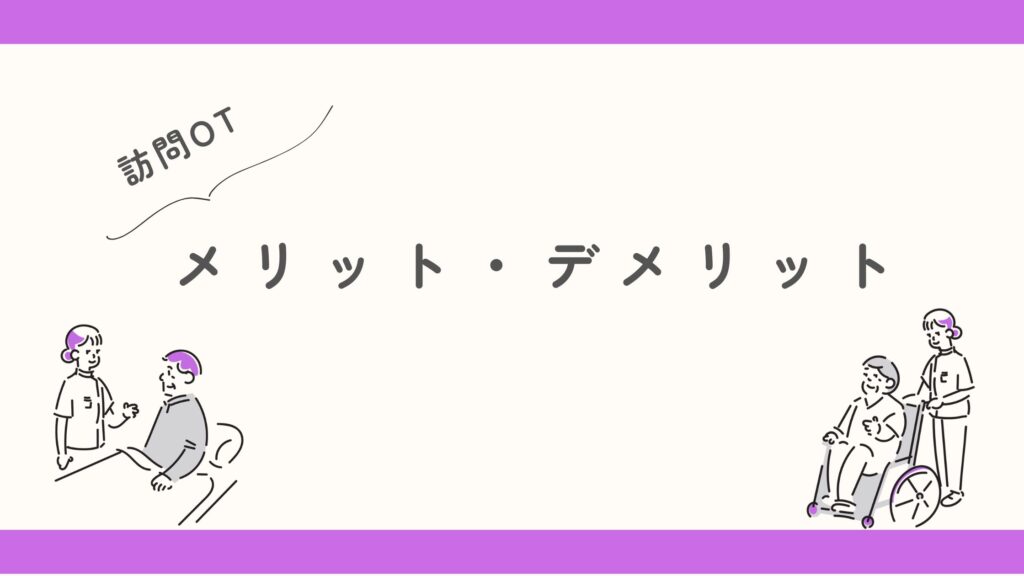
訪問リハビリは、利用者の自宅に直接訪問し、生活環境の中で支援を行うスタイルです。
急性期とは大きく異なり、
「生活に密着した支援」や「自由な働き方」を求める作業療法士に人気があります。
ここでは、訪問リハならではの魅力と注意点を見ていきましょう。
メリット①:自由度の高い働き方ができる
訪問リハの最大の魅力は、
スケジュールの裁量が大きく、時間を柔軟に使える点です。
- 担当利用者のスケジュールを自分で調整できる
- 移動時間も含めて働き方をデザインしやすい
- 勤務形態によっては時短・週休3日なども可能
「家庭と両立したい」「自分のペースで働きたい」という方にとって理想的な選択肢になります。
メリット②:在宅生活に寄り添える支援ができる
病院では見えにくかった「生活の現場」で支援できるのは、訪問ならではのやりがいです。
- 玄関・トイレ・キッチンなど、実際の生活場面での介入
- 家族や介護者と直接話し合いながら支援を調整
- 福祉用具や住宅改修のアドバイスもできる
急性期では介入できなかった



「その人の暮らしを支える支援」が、訪問ではダイレクトに行えます。
デメリット①:孤独感が強く責任も大きい
訪問リハは基本的に“一人で対応する”ため、プレッシャーを感じる場面も少なくありません。
- 利用者の急変やトラブルに即対応しなければならない
- 現場での判断力や臨機応変な対応力が求められる
- チームとの連携が希薄だと、悩みを共有しにくい
「相談できる人が近くにいないと不安」という声も多く、
教育体制やフォローの仕組みが整った事業所を選ぶことが重要です。
デメリット②:スケジューリングや自己管理が必須
自由な分、時間や移動、記録などの“自己管理力”が問われるのも特徴です。
- 訪問件数の調整ミスで空き時間が増える
- 車移動やバイク移動が必須の地域もある
- 記録をためてしまうと、業務が圧迫されやすい
スケジューリングが上手くいかないと、「思ったよりハード」と感じる原因になります。


急性期から維持期へのOT転職
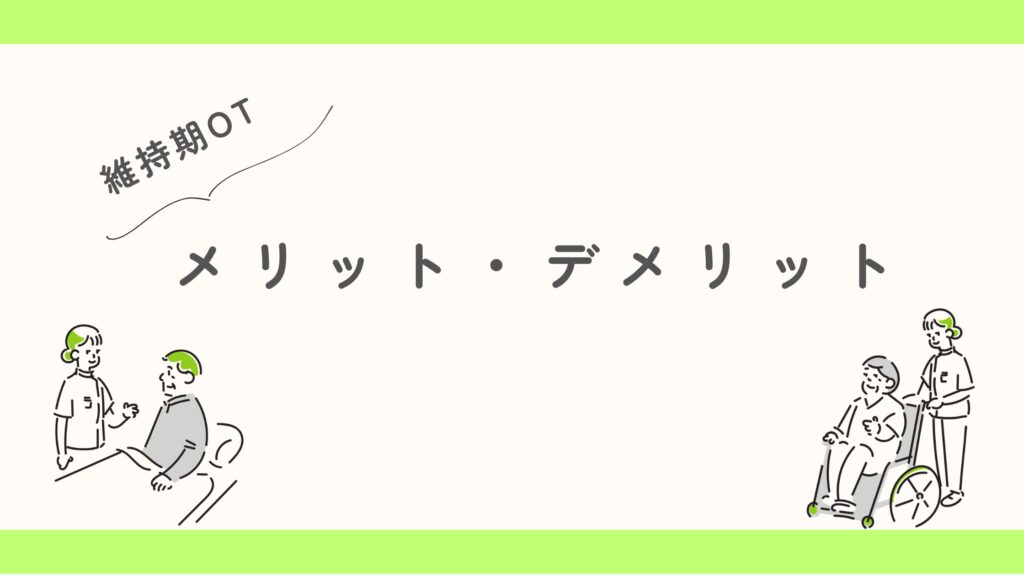
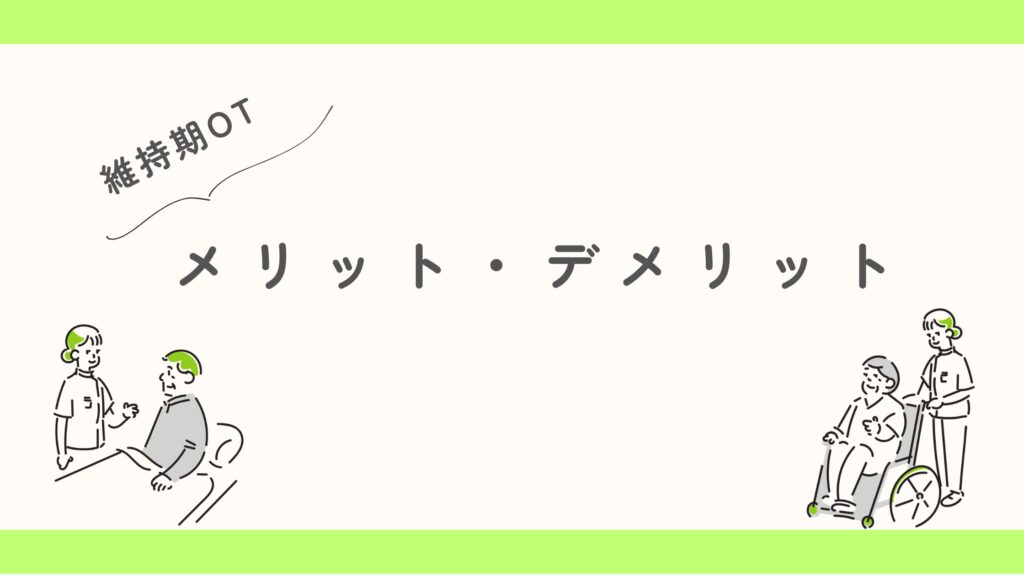
維持期は、老健や特養、デイケアなど、
医療依存度が低い利用者を対象とした生活期の支援を行う場です。
急性期とは対照的な環境で、
「落ち着いて働きたい」「生活支援を重視したい」OTに注目されています。
ここでは、維持期への転職で得られるメリットと、注意すべき点を紹介します。
メリット①:精神的に落ち着いて働ける
急性期のように医療的な緊張感がないため、
精神的なゆとりを持って関われるのが大きな特長です。
- 命に関わる急変が少なく、医師の介入も少なめ
- 曜日単位のスケジュールで業務を組みやすい
- 終業時間が安定していて残業が少ない施設も多い
「気持ちに余裕を持って1人ひとりと関われるようになった」という声は多く、



ワークライフバランスを重視したい方にはぴったりです。
メリット②:生活支援に深く関われる
維持期の支援は、トイレ・食事・更衣・趣味活動など“暮らしそのもの”に直結しています。
- 日常生活での課題を把握しやすい
- 集団活動やレクリエーションでの支援も可能
- 家族や介護職との連携を通じた生活全体の支援ができる
急性期では支援が難しかった“その人らしい生活を整える”アプローチに、より深く関われます。
デメリット①:ルーチン化しやすい
維持期の現場は、
利用者や介入内容が日々大きく変わることが少なく、「マンネリ感」や「刺激の少なさ」を感じる場面があります。
- 週単位でのプログラムが繰り返しになる
- グループ活動の内容が固定化しがち
- 評価やリハビリ内容が形式的になることも
「新しい学びが少ない」「成長が止まっているように感じる」といった悩みを抱えるOTもいます。
デメリット②:医療スキルが衰える可能性も
維持期では医師や看護師との連携が希薄なケースもあり、
医療的な視点やリスク管理スキルを使う機会が減ります。
- モニタリングや急変対応が不要な場面が多い
- 医療処置や疾患への深いアプローチは求められにくい
- 自分から学ぶ意識がないと、専門性が薄れていくリスクがある
医療職としてのアイデンティティを保ちたい方には、少し物足りなさを感じる可能性があります。


急性期から精神科へのOT転職
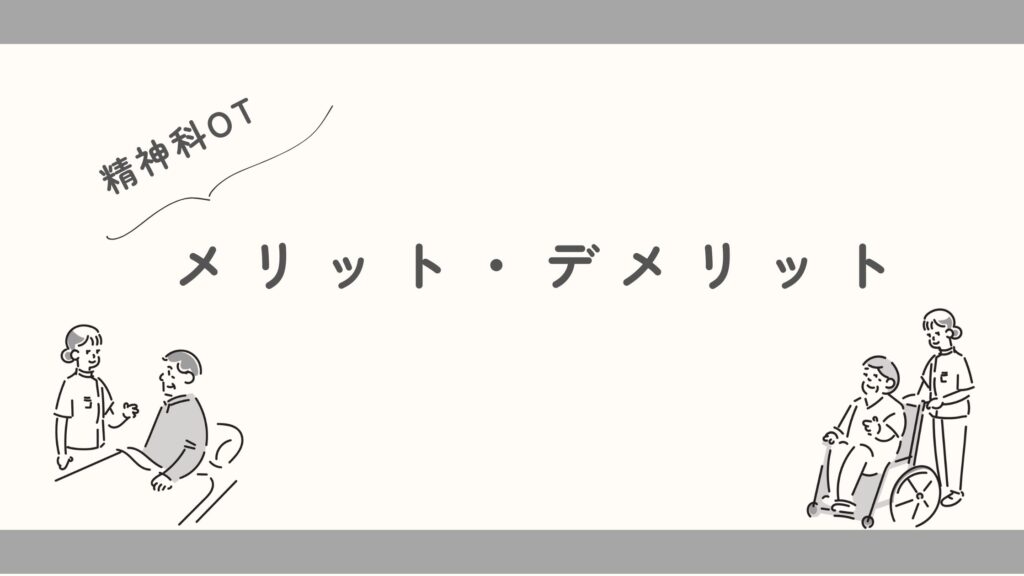
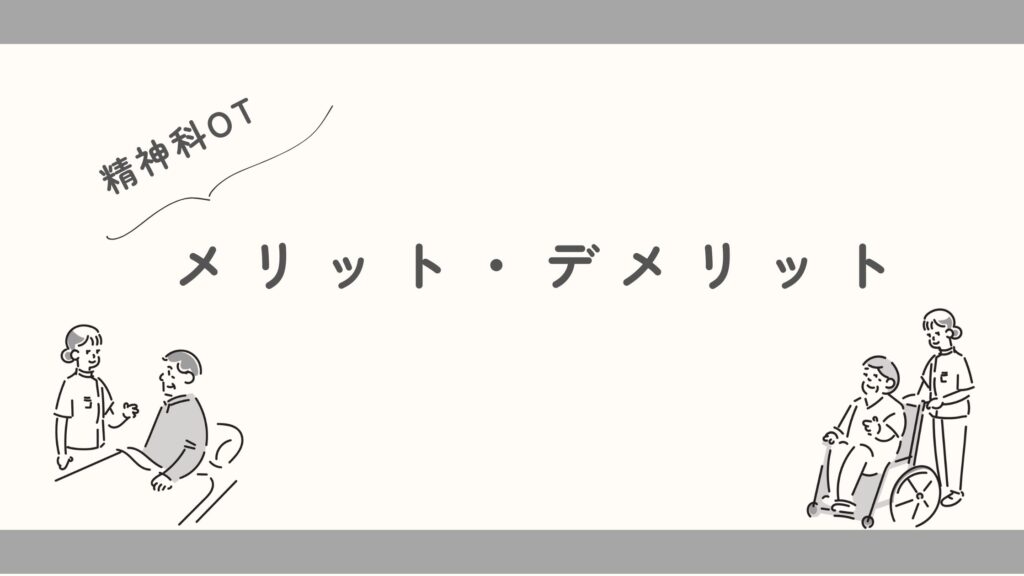
精神科作業療法は、「心の回復」や「関係性による支援」を重視する分野です。
身体機能に特化した急性期とは支援の質が大きく異なり、
ゆっくりとした時間の中で対象者と関係を築いていくアプローチが求められます。
ここでは、精神科への転職によって得られるメリットと、注意すべきデメリットを整理します。
メリット①:じっくり関係性を築く支援ができる
精神科では、急性期と違って
「関係性の構築」が支援そのものになるため、1人ひとりと深く向き合えます。
- 長期的に同じ利用者を担当するケースが多い
- 本人の不安や感情の変化に丁寧に寄り添える
- 話を「聴く力」や「共感的理解」が育つ
「評価・訓練ではなく“存在を支える支援”にやりがいを感じるようになった」という声も多いです。
メリット②:精神的支援スキルが向上する
精神科では、感情の安定・対人関係・自己理解といったテーマに向き合うため、
OTとしての対人支援力が大きく伸びます。
- SSTや認知行動療法をベースとした支援が経験できる
- 対話・傾聴・安心感の提供が支援の柱になる
- 多職種の視点から精神状態をチームでアセスメントする
「話を聴く技術」「表情やしぐさの微妙な変化を捉える感性」が鍛えられます。
デメリット①:身体領域のスキルが活かしにくい
精神科では、身体機能訓練を行う機会が少なく、
急性期で培った技術を活かす場面が限られます。
- 関節可動域や筋力強化などのスキルが使われにくい
- フィジカルの臨床感覚が衰える
- 病院によっては“レクリエーション担当”とみなされることも
医療職としての専門性や自信を保ちたい方は、役割の明確な職場を選ぶ必要があります。
デメリット②:OTとしての役割が曖昧な場合もある
精神科の現場では、作業療法=手芸・創作活動といったイメージが強く、
専門性を発揮しづらい環境も一部存在します。
- 他職種からの理解が得られにくい
- 作業の目的や意味を問われず、形式的な支援になることも
- 支援の「成果」が見えにくく、モチベーションが保ちづらい
自ら役割を築く力・言語化する力が求められる領域です。


分野別比較表|どんな人がどの分野に向いている?


急性期からの転職といっても、
回復期・訪問リハ・維持期・精神科の4分野はそれぞれ特性が異なり、向いている人のタイプも変わります。
ここでは、性格・働き方の志向・キャリア観に応じた分野の選び方を、比較表で整理します。
性格・価値観で見る向き不向き
| 分野 | 向いている人の特徴 |
|---|---|
| 回復期 | 即戦力として活躍したい/医療現場でチーム連携を深めたい人 |
| 訪問リハ | 自由度を重視/自分の裁量でスケジュールを組みたい/在宅支援に興味がある人 |
| 維持期 | 落ち着いた環境で丁寧に支援したい/生活支援を重視/仕事とプライベートを両立したい人 |
| 精神科 | 心のケアに興味がある/関係性を重視した支援がしたい/対話力を高めたい人 |
ワークライフバランス・やりがい・収入面での傾向
| 項目 | 回復期 | 訪問リハ | 維持期 | 精神科 |
|---|---|---|---|---|
| 残業の少なさ | ||||
| 収入の傾向 | ||||
| やりがいの質 | ||||
| スキルの汎用性 |
どの分野にもメリット・デメリットはありますが、



「今の自分にとって大切な価値観は何か?」を明確にすることで、最適な選択が見えてきます。
まとめ|急性期経験を活かして、次のステージを選ぼう
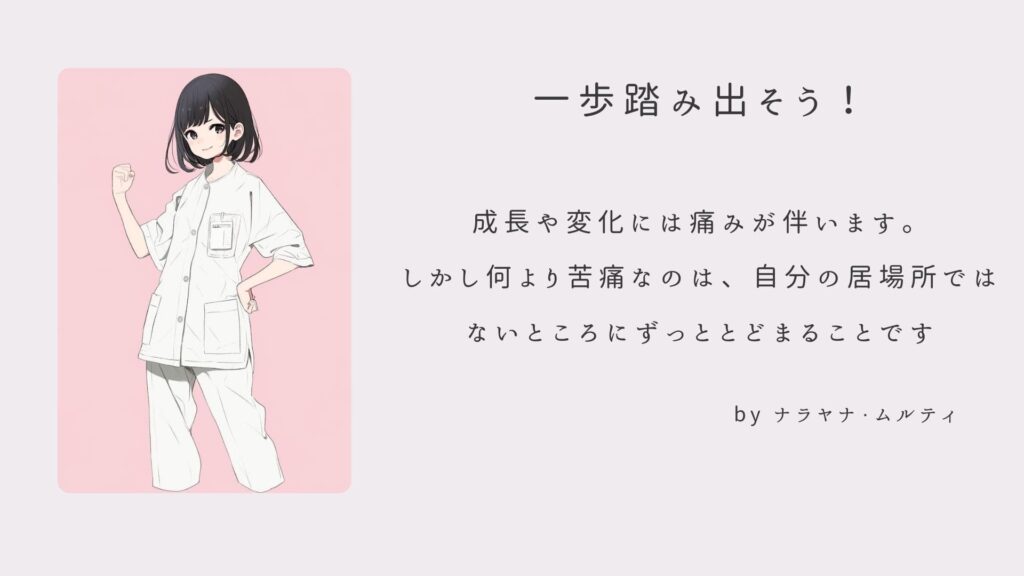
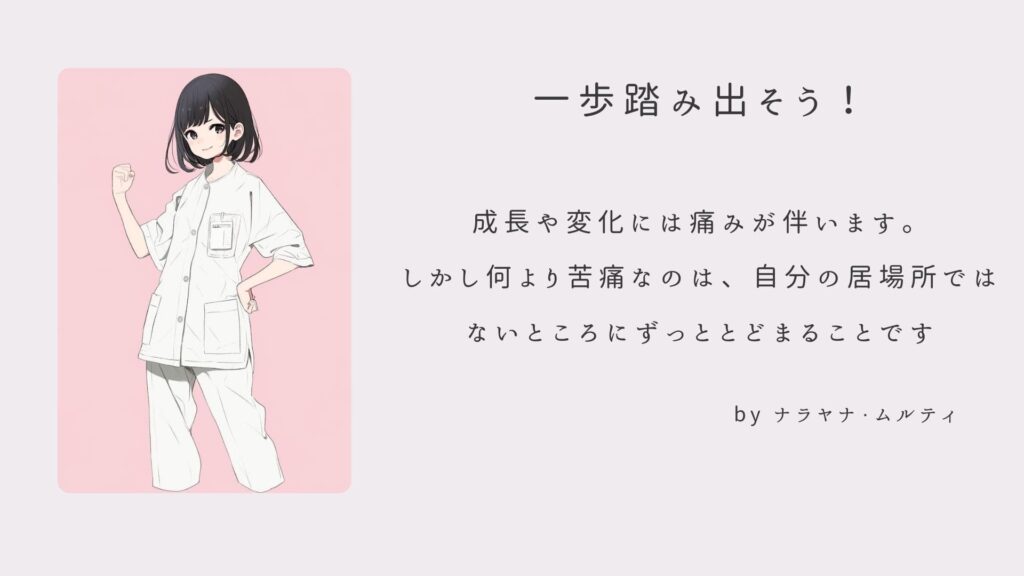
急性期での経験は、作業療法士としての判断力・観察力・連携力といった土台を培える貴重なキャリアです。
その経験をどう活かすかによって、
次のフィールドでのやりがいや成長の仕方は大きく変わります。
- 今の自分に合った働き方がしたい
- 将来のために幅広い経験を積みたい
そう考えたとき、急性期を出ること=キャリアの後退ではありません。
むしろ、違う環境でしか得られない学びややりがいに出会えるはずです。
迷ったらまずは、見学・相談・情報収集から始めてみてください。



あなたにぴったりの次のステージは、必ず見つかります。
\ 各分野の転職先を多数掲載中! /
OTにおすすめの転職サイト3選を見る