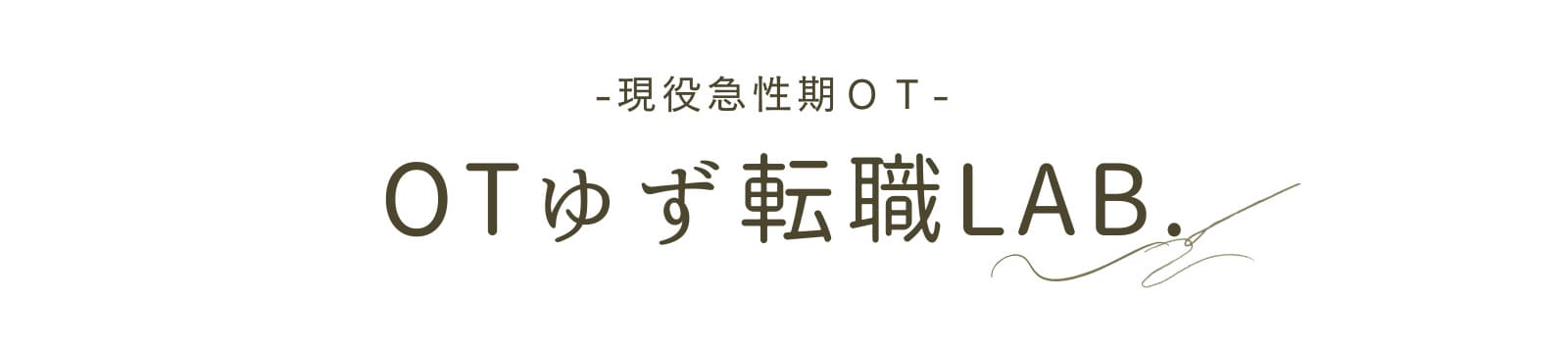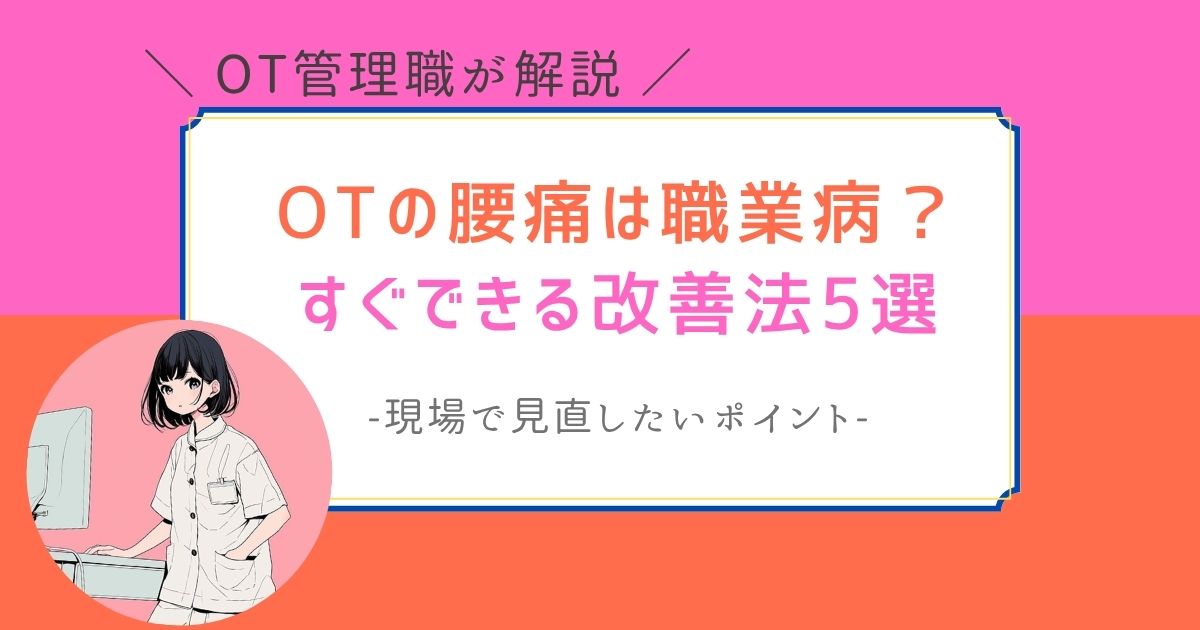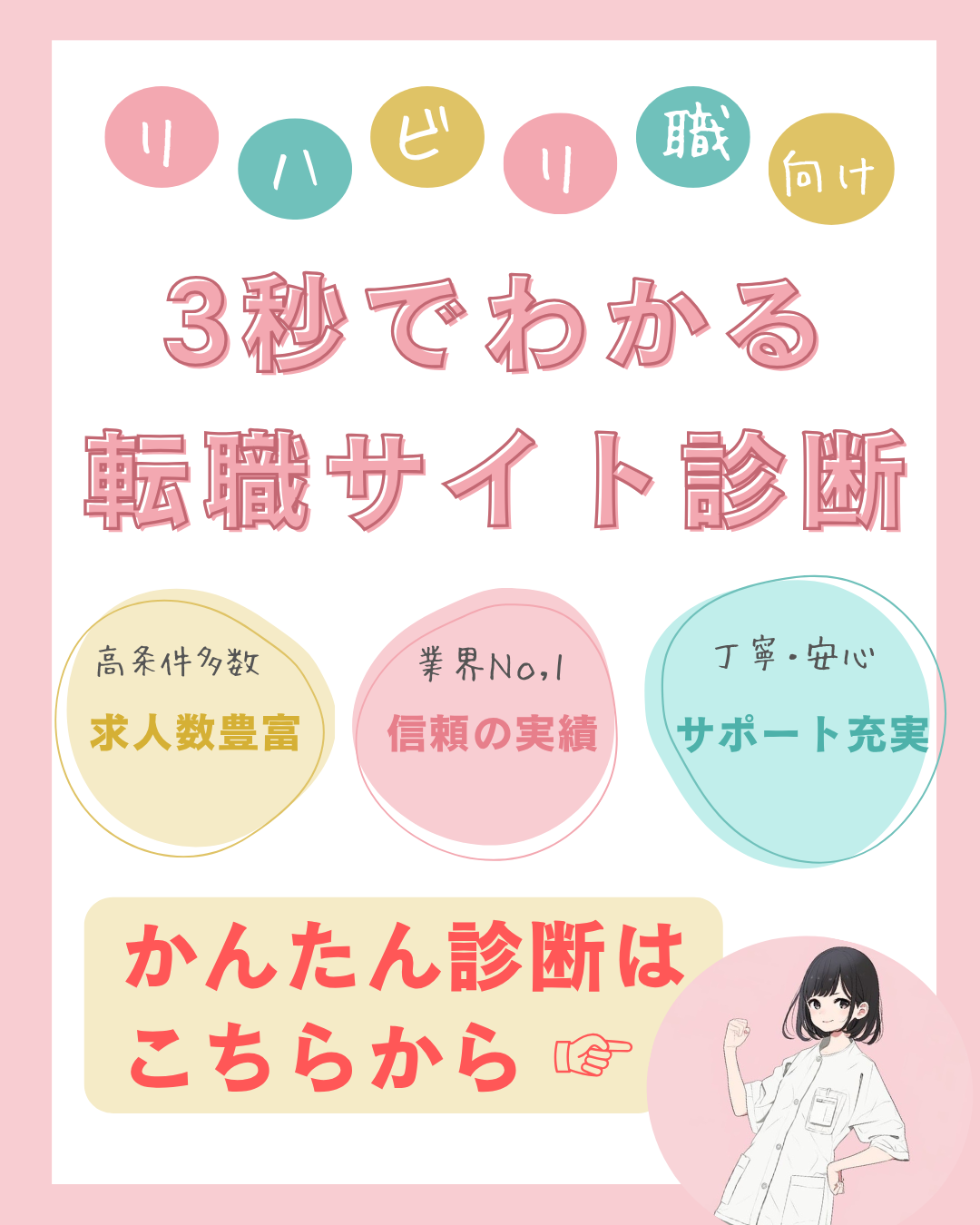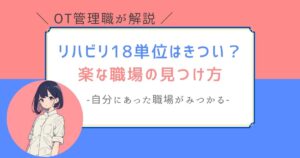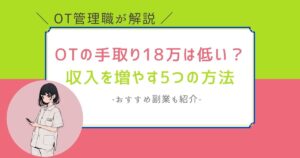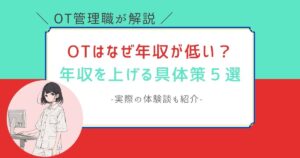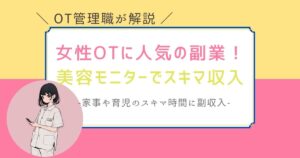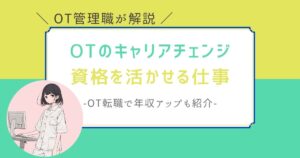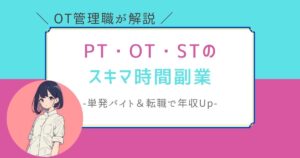作業療法士として働く中で、
 OTゆず
OTゆず「腰痛は職業病みたいなもの」とあきらめていませんか?
現場では患者さんの移乗や介助、前かがみでの作業が多く、
毎日のように腰に負担を感じている方も多いはず。
実際、最新の調査でも作業療法士の約半数が腰痛を抱えているというデータがあります。
でも、腰痛を“仕方がない”と放置してしまうと、キャリアの断念や生活への支障にまでつながりかねません。
本記事では、
現役OT・管理職の視点から「すぐできる腰痛対策と改善法」をエビデンスや実体験を交えて解説。
さらに「どうしても現場で改善しない場合は、“腰痛リスクが低い職場”への転職も前向きな選択肢」
という“働き方ごと見直す方法”まで提案します。



今の悩みを少しでも軽くしたい方、長く健康に働き続けたい方は、ぜひ最後までご覧ください。


- OT歴15年以上、急性期OT
- 役職名は、係長
- 転職歴2回
- 回復期→在宅→急性期(現在)
- 2回の転職で年収250万Up
- 面接対策・転職ノウハウを発信
- (@yuzu_ot_reha)
作業療法士の腰痛は職業病?調査で明らかになった現状
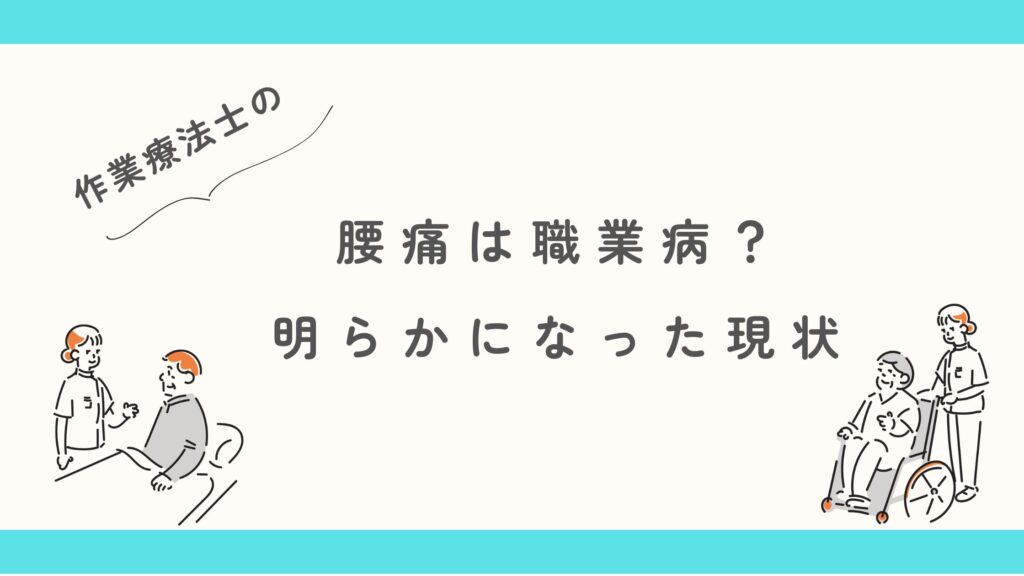
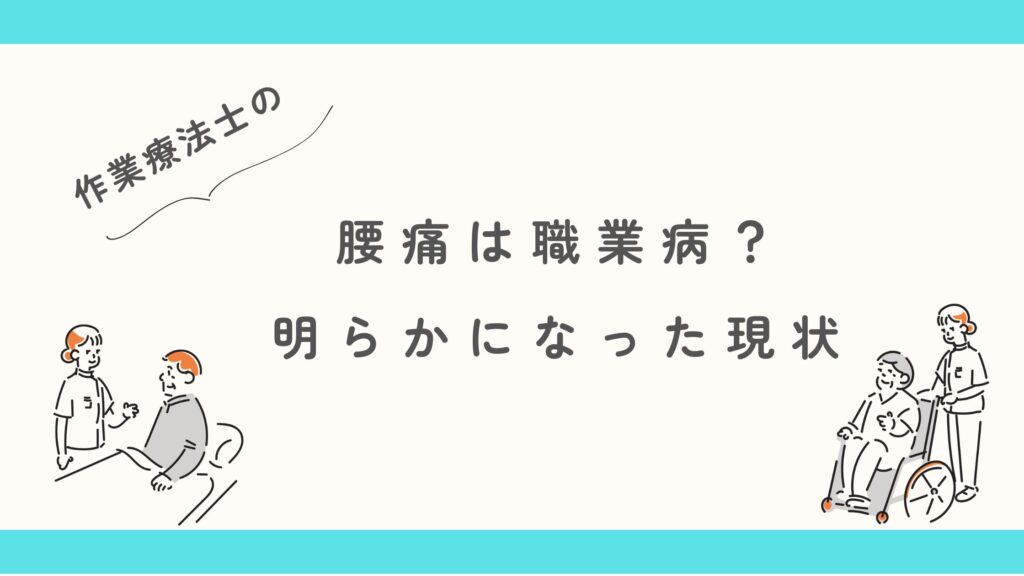
作業療法士にとって腰痛は、まさに“職業病”といえるほど多くの人が抱える問題です。
近年の調査によると、
作業療法士の腰痛有訴率は52.3%と、実に2人に1人以上が腰痛を経験している現実があります。
腰痛有訴率は52.3%―現場で何が起きているか
厚生労働省や学会研究※によると、
施設によっては14.3%~66.7%と差があるものの、
多くの現場で腰痛に苦しむOTが多いことは明らかです。
さらに、経験年数が浅い若手だけでなく、ベテランでも腰痛に悩むケースが目立ち、



性別や年齢にかかわらず注意が必要であることが分かっています。
※(第50回日本理学療法学術大会「リハビリテーション職における腰痛実態調査」)
腰痛が多い主な原因と介助現場のリアル
作業療法士の腰痛は、日々の業務に潜むいくつかの要因から発生しています。
具体的には、
- 移乗や体位変換などで“抱え上げ”介助を行う場面が多い
- 一人で重度患者の対応をせざるを得ないケースが多い
- 前かがみ・中腰など無理な姿勢での作業が続く
- 時間に追われ、正しいボディメカニクスを意識しづらい
学会抄録でも
- 「一人で介助しないといけないと感じている者は77.1%」
- 「抱え上げを行っている者は53.8%」
と高率であることが指摘されています。



福祉用具やリフトの活用率も低く、どうしても体へ負担が集中してしまうのが現状です。
他職種との比較とキャリアへの影響
PTOTSTの間で、腰痛の発生率に有意差は見られなかったものの、
リハ職全体が腰痛リスクの高い職種であることが明らかになっています。
腰痛を我慢しながら働き続けると、
- パフォーマンスの低下
- 欠勤や休職の増加
- キャリアの断念や転職リスクの増加
といった影響につながりかねません。
だからこそ、



「腰痛=仕方ない」とあきらめず、今できる対策や環境改善がとても大切です。
\働きやすい職場が多数掲載中/
OTに人気の転職サイト3選腰痛予防は教育がカギ!現場で見直したいポイント
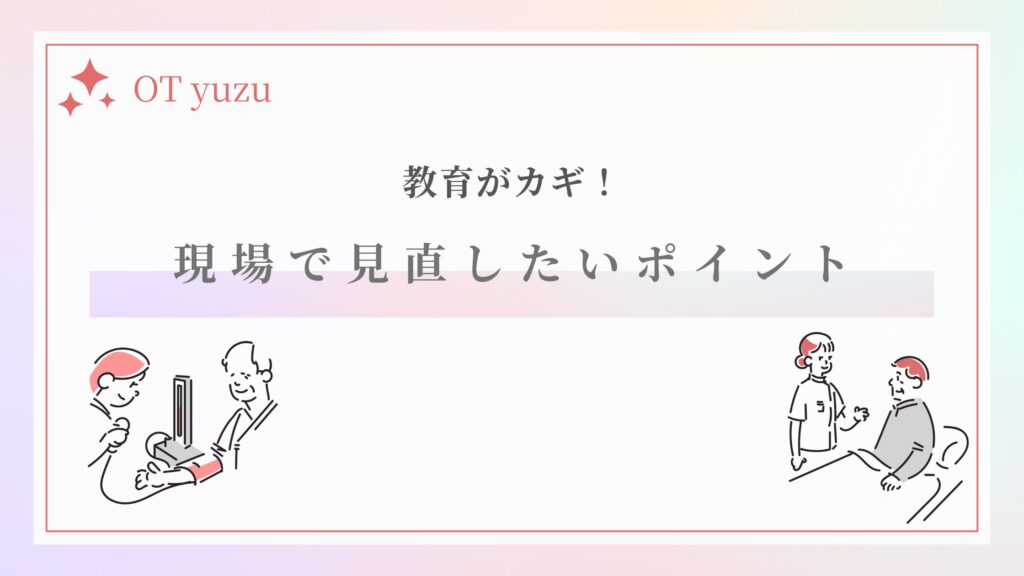
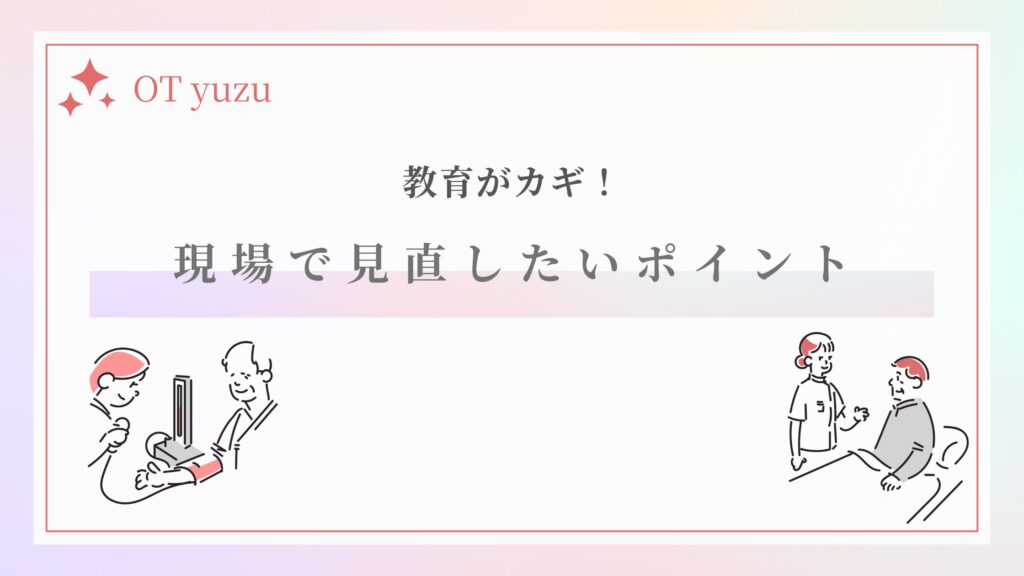
作業療法士の腰痛対策は、個人の努力だけでは限界があります。
最新の調査でも
というデータが示されており、
教育や職場全体での取り組みが予防の決め手であることが分かっています。
勉強会・研修への参加が腰痛リスクを半減させる理由
腰痛予防の勉強会や研修では、
- 正しいボディメカニクス
- 負担の少ない介助方法
- セルフケアのポイント
などを体系的に学べます。
調査では
勉強会に参加したことがない人の腰痛有訴率は64.6%
リハビリテーション職における腰痛実態調査
参加経験がある人は35.4%
と明らかな差があり、知識や意識のアップデートが腰痛リスクを半減させることが分かります。
現場の声としても、
「正しい方法を学ぶと、自分の体を守る意識が高まった」
「新しい福祉用具の使い方やコツを知ることで、無理な姿勢が減った」
といった実感が多いです。
「一人で抱え上げ」はNG!チームケアの重要性
作業療法士の業務は、
どうしても「一人で何とかしなければ…」と頑張りすぎてしまいがちです。
しかし、
大切なのは、
「2人以上で介助する」
「困ったときはチームで声を掛け合う」
という職場の雰囲気づくり。
一人での無理な介助は、本人だけでなく患者さんにもリスクを伴います。



上司や同僚と相談しやすい環境を整え、チームワークで腰痛予防に取り組むことが重要です。
福祉用具の活用と環境整備の現実
福祉用具(リフト・アームレスト付き車いす等)の導入は進んできましたが、
実際に“月1回以上使っている”と答えた作業療法士は7.3%と低い水準でした。
これは
- 「導入されていても使い方を知らない」
- 「忙しさから活用できない」
など、現場と制度のギャップが原因です。
職場としては、
福祉用具の使い方研修やマニュアル整備を強化することが有効ですし、
個人としても「使えるものは遠慮なく活用する」という意識が腰痛リスクを減らします。
すぐできる!作業療法士の腰痛対策&改善法5選
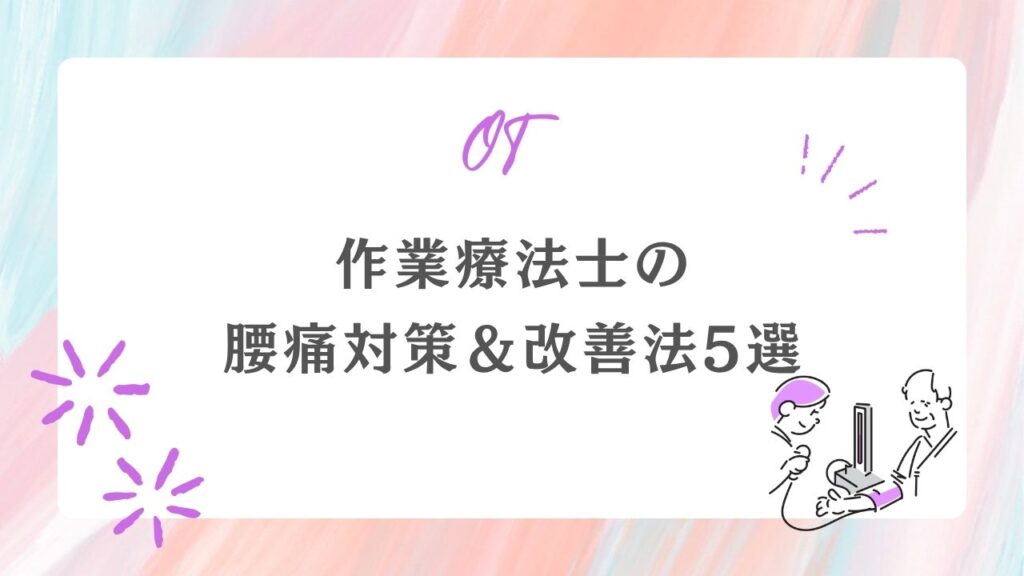
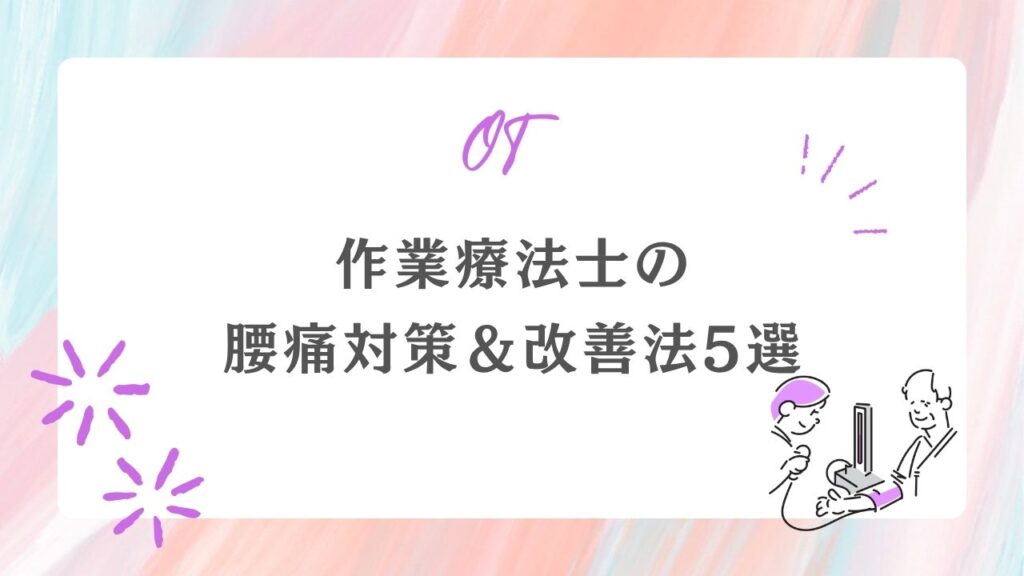
日々の現場で腰痛を防ぐためには、
今日から実践できる小さな工夫の積み重ねが重要です。
ここでは論文・現場経験・管理職の視点もふまえて、
すぐに効果が期待できる腰痛対策と改善法を5つ厳選してご紹介します。
正しいボディメカニクスと抱え上げ回避
移乗・体位変換・介助の場面で正しいボディメカニクスを意識するだけで、腰への負担は大幅に減ります。
- 「膝を曲げて腰を落とす」
- 「体をねじらない」
- 「患者さんの重心に近づく」
など基本動作を日々確認しましょう。
職場で定期的にボディメカニクスやトランスファーの研修があれば、
必ず参加して“我流”のクセを見直すのがおすすめです。
定期的な腰痛予防ストレッチ・セルフケア
ストレッチやセルフケアは、1日の負担をリセットするために不可欠です。
現場でおすすめの簡単ストレッチ例を紹介します。
- 仕事前・休憩中・帰宅後に背中や腰の筋肉をゆっくり伸ばす
- 腹筋・背筋のバランスを意識した筋トレを習慣化する
- 入浴や温熱で血行を促進し、筋緊張をほぐす
セルフケアのポイント(例)
| タイミング | 具体的な方法 |
|---|---|
| 出勤前 | 軽くストレッチ・深呼吸 |
| 休憩中 | 体側伸ばし・軽い屈伸運動 |
| 退勤後 | 湯船で温める・寝る前の軽い体操 |
“短時間でも毎日続けること”が腰痛予防のコツです。
チームで協力!2人介助・助け合いの徹底
先ほども触れましたが、
「一人で頑張りすぎない」ことが腰痛リスクを劇的に減らします。
- 必要な場面では2人以上で介助を徹底
- 周囲に“手伝ってほしい”と素直に声をかける
- 忙しい日ほど“お互い様”の意識を持つ
これらは自分だけでなく、患者さんの安全にもつながります。



職場全体で助け合う雰囲気をつくることが、慢性的な腰痛予防の近道です。
勤務中のこまめな休憩・セルフモニタリング
休憩を軽視してしまうと、知らず知らずのうちに体へダメージが蓄積されます。
- 1~2時間に一度はストレッチや姿勢リセットの時間をとる
- 腰に違和感を感じたら、早めに業務量を調整
- 「今日はちょっと重いな…」と気づいたらすぐ無理をしない
“自分の体調をこまめにチェックする”ことが、
重症化予防・長期的なキャリア維持にもつながります。
上司や産業医に早めに相談し働き方を見直す
「痛みが長引く」「慢性化してきた」と感じたら、早めに上司や産業医・外部サポートに相談しましょう。
- 無理せず業務調整やシフト変更を相談する
- 職場の産業医や人事部の健康相談窓口を活用
- 業務内容や環境自体に課題があれば、思い切って転職も視野に
職場が腰痛予防に積極的でなかったり、
負担の大きい働き方が続く場合は、「自分の健康を守るための転職」も前向きな選択肢です。
\あなたに合った職場が見つかる/
OTに人気の転職サイト3選体験談|私が実践した腰痛対策と現場での気づき


私自身、現場での介助や移乗、長時間の前かがみ姿勢が続くなかで、
「これは本当に腰に悪い…」と何度も感じてきました。
実際に軽い腰痛を繰り返しながら、
対策や働き方を見直すことで、大きなトラブルを防ぐことができた経験があります。
腰痛を経験したからこそわかったこと
腰痛が出始めた頃は、
「まだ若いから大丈夫」「少し休めば治る」とつい油断してしまいがちでした。
しかし、症状が長引くにつれ、日々の介助や患者さん対応にも集中できなくなり、



このままでは仕事そのものが続けられなくなるかも…
と強い危機感を持つようになりました。
特に“抱え上げ”や一人介助が当たり前の雰囲気では、無理が積み重なって慢性化しやすいと実感しました。
実際に効果があった取り組み・工夫
✅ボディメカニクスの徹底
職場の研修やマニュアルを活用して、自分の体の使い方を徹底的に見直しました。
特に「膝を曲げて持ち上げる」「重心を近づける」「無理な動作をしない」ことを毎日意識。
✅セルフケアの習慣化
朝のストレッチ、勤務中のこまめな体操、入浴後のストレッチを生活のルーティンに。
これだけでも腰のこわばりや違和感がかなり軽減されました。
✅チームへの声かけ
無理せず「助けてほしい」と言えるようになったことで、
業務そのものもスムーズになり、周囲との連携も良くなりました。
✅上司への相談と環境調整
慢性的な痛みが強くなったときは早めに上司へ相談し、
患者さんの配置や担当業務を一時的に調整してもらいました。
✅環境を変える選択も
どうしても職場環境が変わらない場合は、転職も前向きな選択肢と考えるようになりました。
実際、腰痛予防教育やチームケアが徹底されている職場に移ったことで、
仕事への不安も大きく減り、長く健康に働き続けられるようになったと感じます。
まとめ
腰痛は「自分の工夫+周囲の協力+職場の体制」



この3つがそろってはじめて、本当の予防と改善につながると強く実感しています。
まとめ|作業療法士の腰痛対策で“長く健康に働く”には
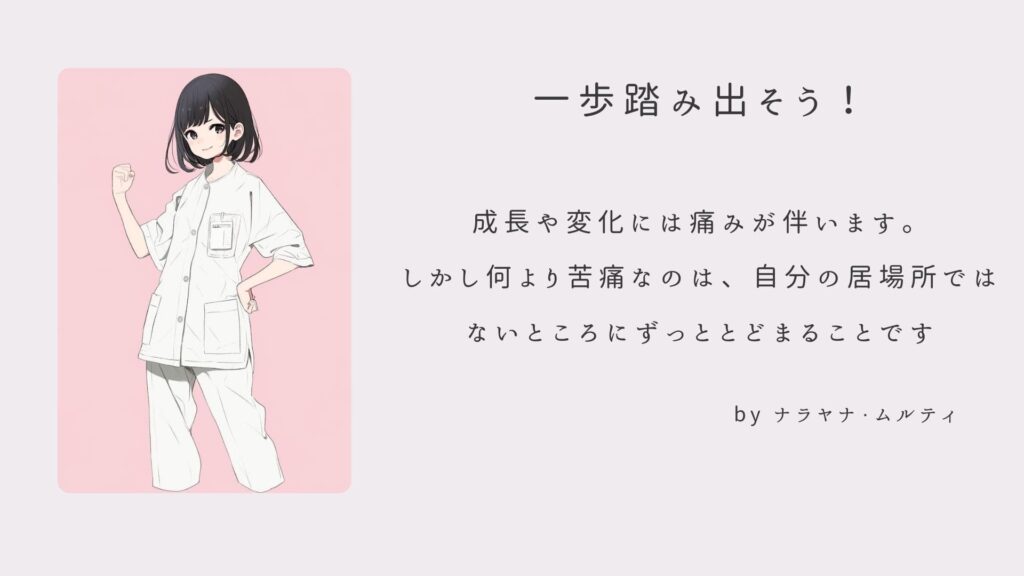
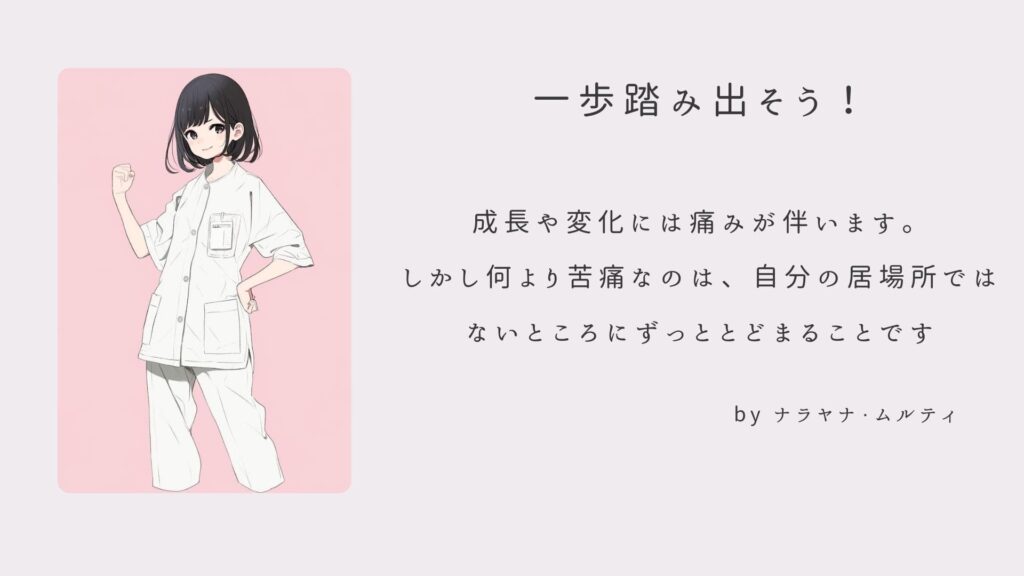
作業療法士にとって、腰痛は多くの人が直面する“職業病”ですが、
決して「仕方がない」と諦める必要はありません。
腰痛予防は、自分ひとりの努力だけでは限界があります。
- 勉強会や研修で学ぶ
- 2人介助や福祉用具を活用する
- 困ったら上司や同僚と相談する
こうした意識や働きかけが、自分の健康を守る第一歩になります。
それでも職場環境や働き方がどうしても合わない、慢性的な腰痛が改善しない場合には、
“腰痛リスクの低い職場”への転職も前向きな選択肢です。


- PTOTSTワーカー
- PTOT人材バンク
- レバウェルリハビリ
などの転職エージェントを活用すれば、
実際の職場の雰囲気や定着率までしっかり把握した上で、あなたに合った職場を選ぶことができます。
腰痛をきっかけに、「長く健康に働けるキャリア」を本気で考えてみませんか?



無理なく続けられる環境づくりを、ぜひ今日から始めてみてください。