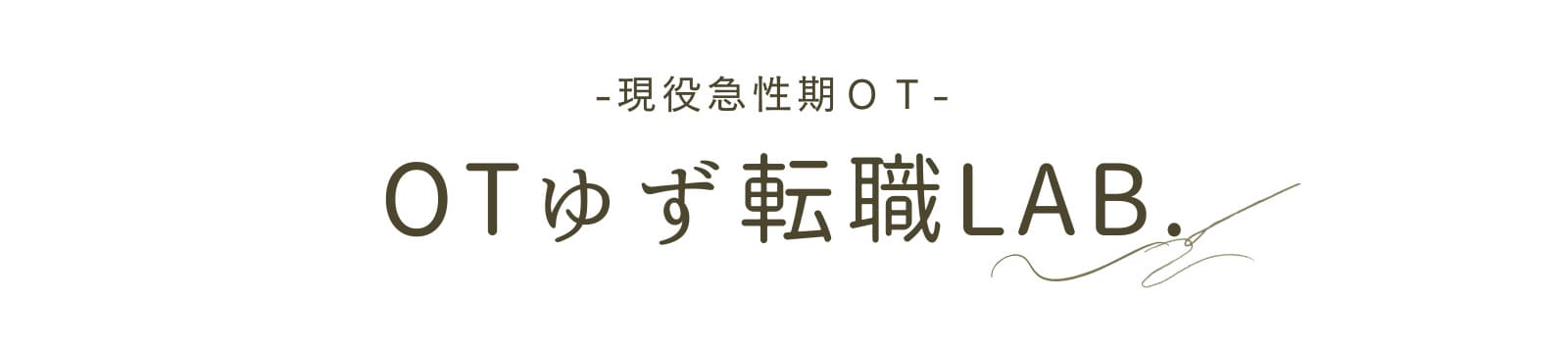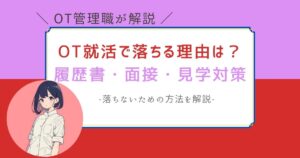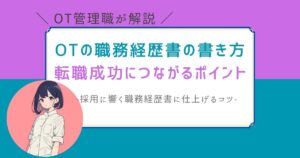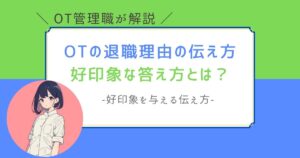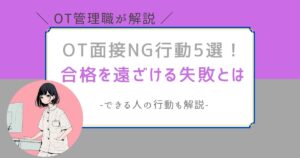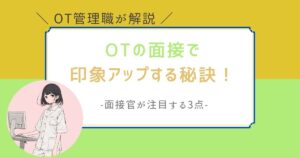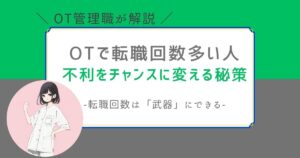転職するOT
転職するOT履歴書なんて形式さえ守ればOKでしょ?
そう思っている作業療法士の方は、実はとても多いです。
しかし、履歴書の内容は“その人の仕事への向き合い方”を如実に映し出す鏡。
現役OT管理職として採用の現場に立ってきた中で、
「この人は通る」「この人は落ちる」と判断する決定的な違いは、たしかに存在しました。
この記事では、
履歴書で落とされる人の“あるある”や、通る人に共通する書き方のコツを、採点する立場から本音で解説します。



さらに、無料でカンタンAIを使って履歴書を作成できる便利ツールも紹介します♪


- OT歴15年以上、急性期OT
- 役職名は、係長
- 転職歴2回
- 回復期→在宅→急性期(現在)
- 2回の転職で年収250万Up
- 面接対策・転職ノウハウ情報を発信
作業療法士の履歴書は書き方が大事
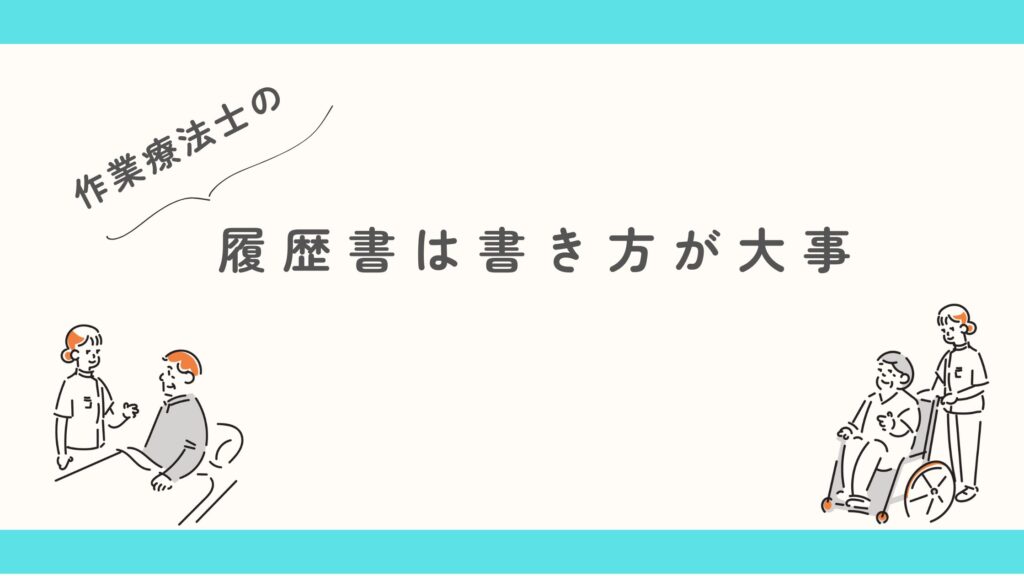
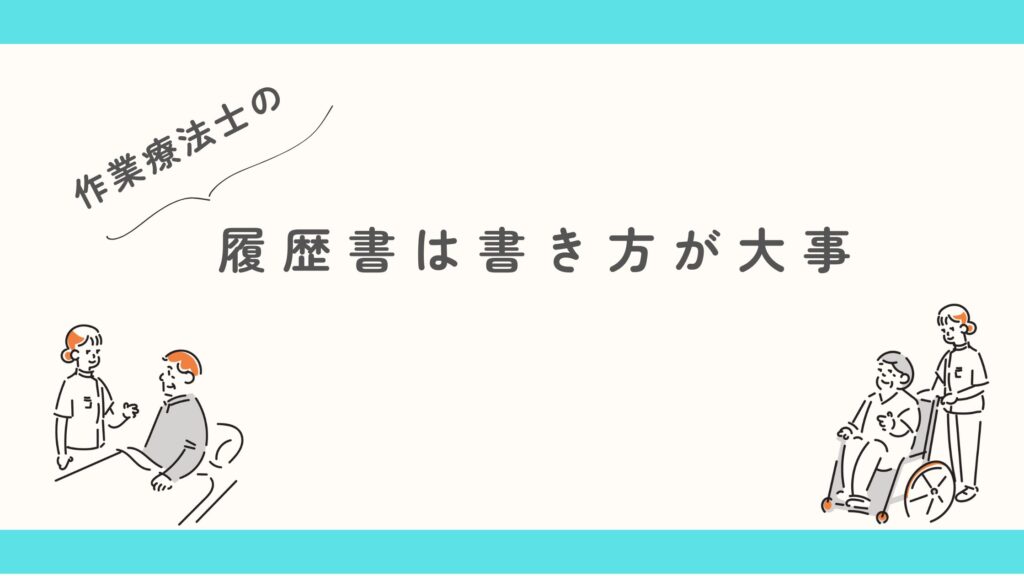
履歴書は、単なる“自己紹介シート”ではありません。
- 採用担当はどこを見ているのか?
- 履歴書だけで「不採用」を決めることもある
- 書類選考を通るには視点の転換が必要
むしろ、採用担当にとっては「この人を面接に呼ぶかどうか」を判断する一次スクリーニングの最重要書類です。
採用担当はどこを見ているのか?
作業療法士の採用において、履歴書のどこが見られているか。
管理職として何十枚と見てきた中で、必ずチェックされるポイントは以下の4つ
- 志望動機に“本気度”が感じられるか
- 自己PRが“仕事への姿勢”に結びついているか
- 書類の見やすさ・整い具合
- 書き手の“考え方”や“人柄”が伝わるかどうか
つまり、単なる事実の羅列ではなく、
履歴書だけで「不採用」を決めることもある
「面接してから判断すればいいのでは?」と思うかもしれませんが、
実際の採用現場では、履歴書の内容次第で“書類落ち”が即決することも稀にあります。
たとえば、
- 志望動機が明らかに使い回し
- 自己PRが抽象的すぎてピンとこない
- 誤字・脱字・空欄が目立つ
- 履歴の整合性が取れていない
こうした書類は、
- 「この人と働くイメージがわかない」
- 「雑な印象がある」
と見なされ、面接に呼ばれる前に落とされてしまうのです。
書類選考を通るには視点の転換が必要
履歴書で差がつく最大のポイントは、
多くの人が、
- 「これまで頑張ったこと」
- 「自分の想い」
を中心に書いてしまいますが、
大事なのは、“その頑張りがどう職場に貢献するか”を読み手がイメージできるかです。
つまり履歴書は、



自分を売り込むものではなく、“相手に届ける”設計が必要な文章なのです。
\履歴書・面接対策もできる/
OTに人気の転職サイト3選通る履歴書と落ちる履歴書の決定的な違い
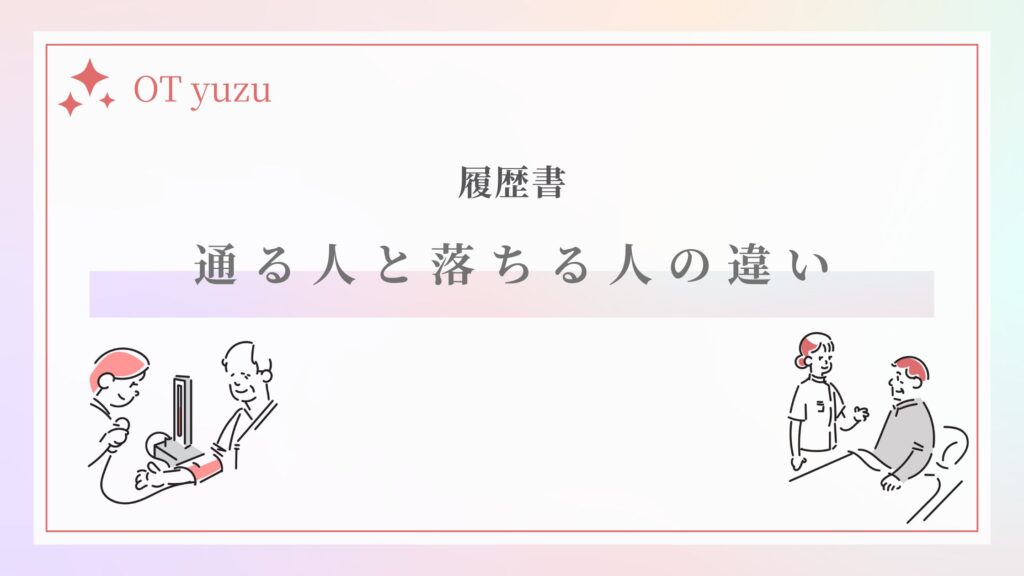
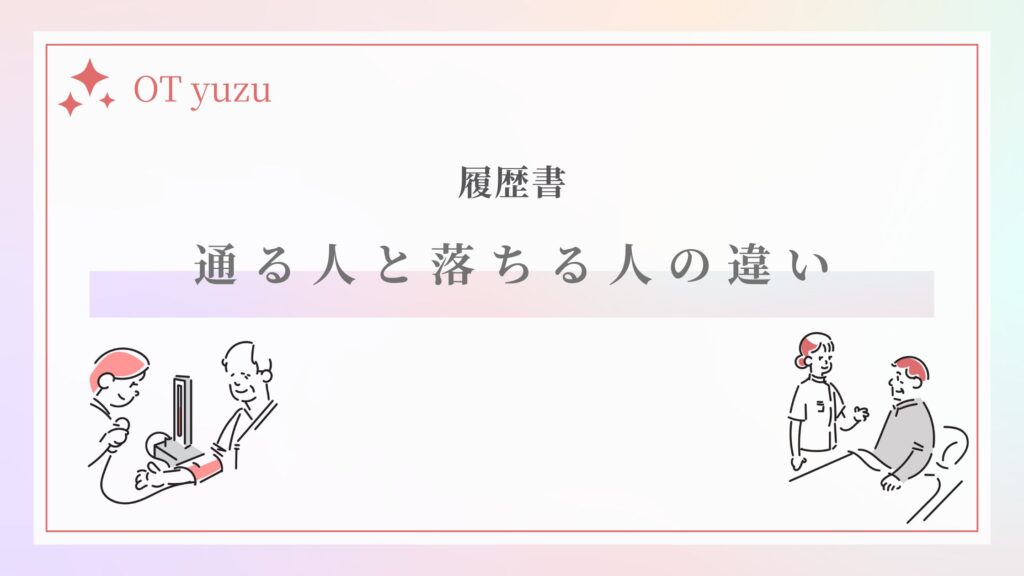
履歴書で見られているのは、内容そのものだけではありません。
- ぱっと見で“伝わる人”と“伝わらない人”
- 誤字・余白・写真…基本ミスが多すぎる
- 「どこでもいいです感」は即バレます
ここでは、管理職として実際に書類選考を行ってきた立場から、落ちる履歴書・通る履歴書の違いを、具体的に解説します。
ぱっと見で“伝わる人”と“伝わらない人”
まず最初に見ているのは、「第一印象として、読みたくなるかどうか」です。
読み手は数十枚単位の履歴書を一気に目を通すため、視覚的な見やすさ・構成の整い方は極めて重要です。
✔ 通る履歴書の特徴
- 適切な余白があり、バランスが良い
- 文章量にムラがなく、読みやすい長さ
- セクションごとの区切りが明確
- 読みやすい字
✖ 落ちる履歴書の特徴
- 文字が詰まりすぎている or スカスカ
- 文字が小さすぎる/雑な印象
- 空欄が目立つ、余白バランスが崩れている
書類は「読む前に“読まれるか”が勝負」です。



内容の前に“見た目”で損している人が非常に多いことを知っておきましょう。
誤字・余白・写真…基本ミスが多すぎる
履歴書での小さなミスは、実はかなり致命的です。
なぜなら、
「患者さんのカルテ記載もこんな感じなのかな…」
「この人、確認力が弱いかも」
と連想されてしまうからです。
よくあるNGポイント
- 誤字脱字
- 記入漏れ・空欄のままの項目
- 顔写真のサイズや貼り方が雑
- 余白を適当に埋めているのがバレる
特に作業療法士のように書類・記録が日常業務の中核を占める職種では、



「書類が整っている=仕事が丁寧」という印象に直結します。
「どこでもいいです感」は即バレます
採用側は「うちの職場を本気で選んでくれているか」を気にしています。
そのため、履歴書から“消去法で応募しただけ”という空気が出ていると、かなりの確率で不採用になります。
よくあるNGポイント
- 志望動機がテンプレのまま
- 施設の特色に一切触れていない
- 自分の希望だけで、相手のニーズが無視されている
採用担当は、「この人が来たら、どう貢献してくれるだろう?」をイメージしたいのです。
履歴書にそのヒントがなければ、面接に呼ばれる可能性は限りなく低くなります。
\履歴書で合格率アップ/
OTに人気の転職サイト3選志望動機は“誰でも書ける内容”では落ちる
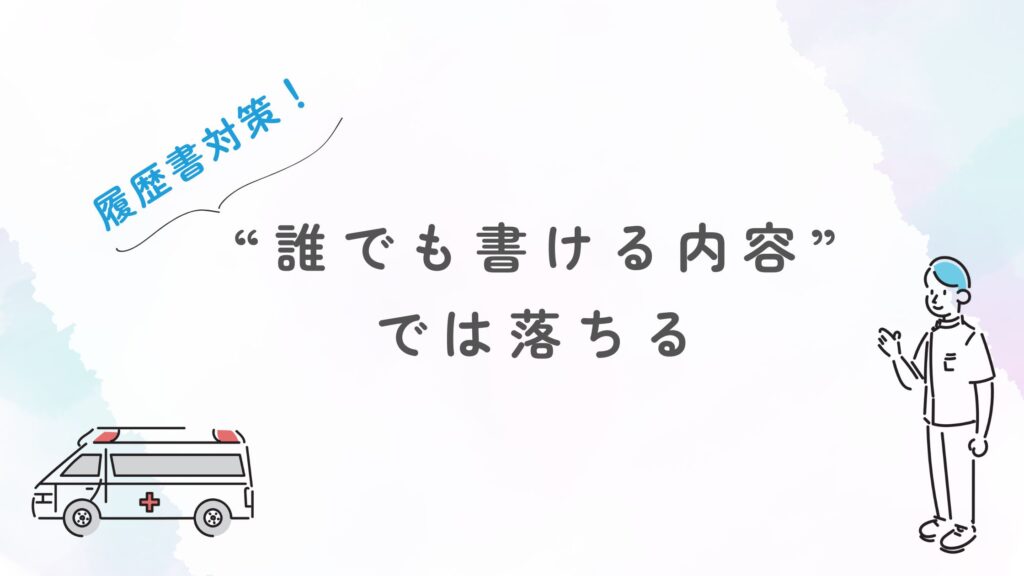
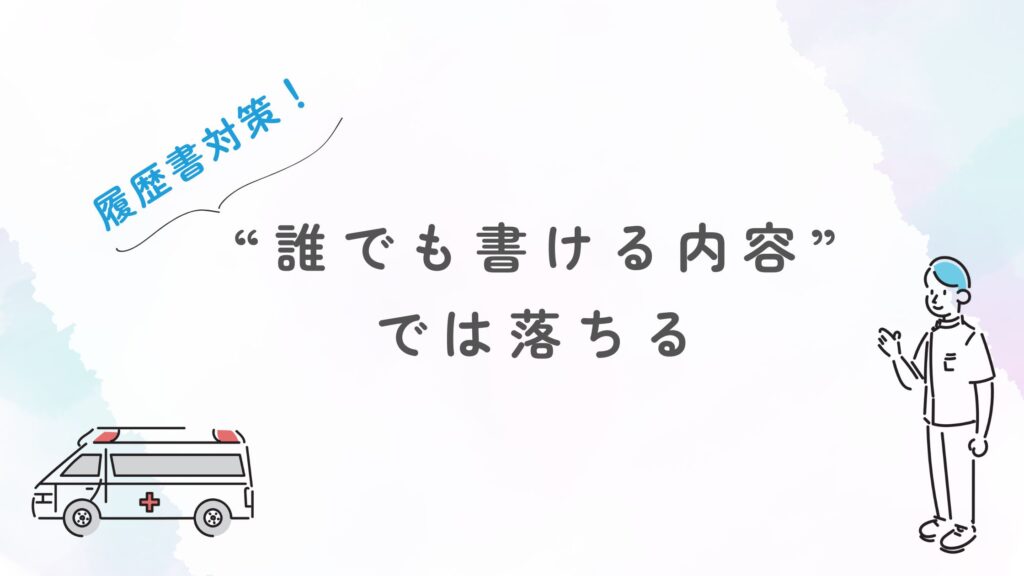
履歴書で最も読まれているのが、志望動機です。
採用担当者がこの欄に求めているのは、「この人がなぜうちを選んだのか」という納得感です。
- コピペ感が出る志望動機は秒で見抜かれる
- 通る志望動機は「〇〇したい」より「〇〇できる」
- 管理職OTが評価した実例・落とした実例
しかし現実には、「どこでも使えるテンプレ志望動機」が多く、“本気度が低い”と判断されてしまうことも少なくありません。
コピペ感が出る志望動機は秒で見抜かれる
たとえば、以下のような志望動機は要注意です。
- 「患者様一人ひとりに寄り添った支援をしたいと思ったから」
- 「地域に根ざした医療を実践されているところに魅力を感じました」
- 「チーム医療を大切にしている点に共感しました」
どれも一見丁寧ですが、
どの職場にも通じるような抽象的な表現で“誰が書いても同じに見える”のが問題です。
面接官側は、



この人、うちの施設の何を調べてきたんだろう?
と疑問に感じてしまいます。


通る志望動機は「〇〇したい」より「〇〇できる」
履歴書で差がつく志望動機は、
「私は〇〇したい」ではなく、「これまでの経験を活かして〇〇できる」という具体的な貢献の提案型になっています。
具体例
- 「急性期での経験を活かし、早期ADL獲得を支援する体制に貢献できると考えています」
- 「前職で取り組んだ認知症リハのプログラム開発経験を、貴施設のデイケア運営に活かしたいと感じました」
このように、「自分ができること×応募先の特徴」をセットで書くと、



この人はうちを理解しているという印象がグッと高まります♪
管理職OTが評価した実例・落とした実例
通過した志望動機(実例)
「前職ではADL評価の標準化に取り組みました。貴施設の“生活にこだわる”という理念に深く共感し、その経験をチーム内での質向上に活かしたいと考えています。」
- 調べた上で書いている
- 経験が具体的
- 貢献意識がある
落とした志望動機(実例)
「患者様一人ひとりに向き合いたいと考え、御施設を志望しました。」
- どこでも言える内容
- 貢献性が見えない
- 具体的な経験や根拠がない
志望動機で差がつくのは“視点”です。
自分の希望を語るだけでなく、「相手にとって自分は何者か?」を伝える。



これが、面接に呼ばれるかどうかの分かれ道となります。
自己PRは“性格”より“仕事でどう活かすか”


採用担当が見たいのは「どんな性格か」よりも、
「その性格がどう仕事に影響するか」「どんな貢献ができるのか」です。
「明るく元気です」は評価されない理由
多くの履歴書に書かれている「明るい性格」「誰とでもすぐに打ち解けられます」。
悪い印象ではないですが、



で、だから何ができるの?
と感じてしまうのが本音です。
たとえば、
「私は明るく元気な性格です。周囲とすぐに打ち解け、誰とでも協力して業務にあたることができます。」
という一文は、ふわっとした印象で終わってしまいます。
面接官が知りたいのは、「その明るさがチームでどんな成果に結びついたか」です。
評価される自己PRの書き方はこちら


経験より「どう考えて動いてきたか」が伝わるか
履歴書に実績を書くときは、
ただ“やったこと”を列挙するのではなく、「どう考えてその行動を選び、何を得たか」まで書けると一気に説得力が増します。
たとえば、
「新人指導を担当した際、業務の流れだけでなく“なぜそうするのか”まで伝えることで理解が深まり、指導期間が短縮できました。」
このように、“自分の行動→相手の変化→成果”という流れで書けると、



採用側も「この人は考えて動けるタイプだ」と判断しやすくなります。
迷ったら「問題→工夫→結果」の構成で書く
「何を書けばいいかわからない…」という人におすすめなのが、PREP法や三段構成(問題→工夫→結果)です。
以下のように組み立てると、自然に伝わる自己PRになります。
- 問題:「業務が煩雑で申し送りが漏れることがありました」
- 工夫:「視覚的な申し送り表を作り、情報を整理しました」
- 結果:「確認ミスが減り、チーム内でも共有がスムーズになりました」
この構成は、“自分の強み”を具体的なエピソードで裏付けることができるため、信頼感を得やすくなります。
自己PRは、“性格の羅列”では差がつきません。


【作業療法士向け】AIで履歴書を簡単に作れる「レジュマップ」とは?


転職活動で悩むポイントのひとつが「履歴書・職務経歴書づくり」。
特にOTの場合、専門用語や経験の書き方に迷う方が多いのではないでしょうか。
そんな悩みを解決してくれるのが、
AIが履歴書を自動で作成してくれる無料サービス 「レジュマップ」 です。



パソコンやスマホから、わずか数分で完成度の高い書類を作成できます♪
レジュマップの特徴:AIが履歴書を自動で仕上げる


レジュマップは、AI技術を活用して履歴書・職務経歴書を自動で生成するサービス。
質問に答えるだけで、あなたの経歴に合った自然な文章をAIが作成してくれます。
主な特徴
- AIが志望動機や自己PRを自動生成
- 業界別のテンプレートが豊富
- 人材紹介のプロが監修
- 作成からダウンロードまで完全無料
「AIがどこまでやってくれるの?」と不安に思う方もいるかもしれませんが、
実際にはAIが土台を作り、それを自分で微調整するだけ。



文章力に自信がなくても、見栄えがよく、伝わる書類が短時間で完成します。
医療・リハビリ業界にも対応!作業療法士の転職にも最適


レジュマップは、医療・介護・リハビリ分野にも完全対応。
作業療法士の経歴やスキルに合わせた例文も豊富に用意されているため、
病院・クリニック・老健・訪問リハなど、どんな職場を希望していても使いやすい設計です。
おすすめな方
- 「ブランクがあって書き方を忘れてしまった」
- 「文章が苦手でお手本を見たい」
- 「短時間で質の高い職務経歴書を作りたい」
作業療法士としてのスキルを的確にアピールできるだけでなく、
「文章が伝わりやすい」「印象に残る」と感じてもらえる仕上がりになります。
無料登録で使える便利機能とメリット


レジュマップは、無料登録をすることでさらに便利に使えます。
- 履歴書・職務経歴書を保存・編集できるマイページ機能
- エクセルやPDFでのダウンロード対応
- 履歴書の添削・面接対策・求人紹介を依頼できるサポート機能
しかも、登録もたったの1分。
メールアドレスと簡単な情報を入力するだけで、すぐにAI作成をスタートできます。



無料登録なしでもカンタンAIで履歴書作成できる♪参考程度に見るだけでも役に立ちます。
\ 履歴書・職務経歴書を「超簡単」に /
医療・介護・リハビリ分野にも完全対応
まとめ|履歴書で“損してる”作業療法士を減らしたい
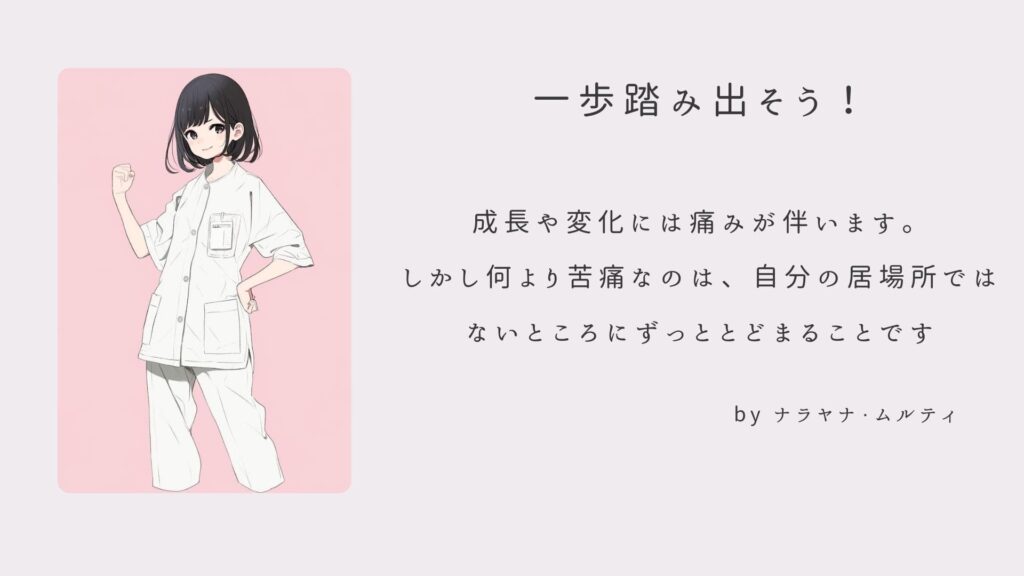
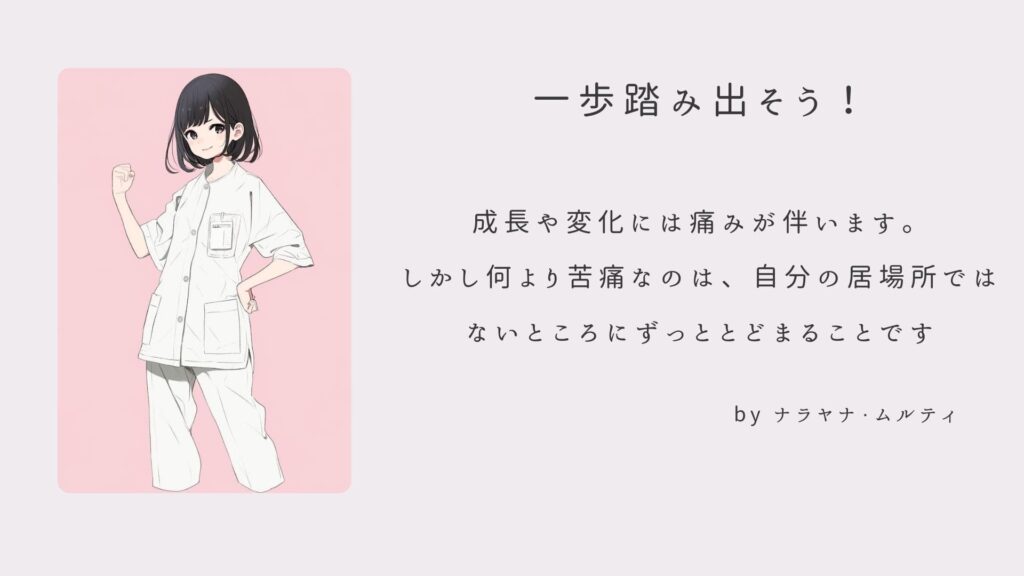
作業療法士の履歴書は、面接へ進めるかどうかを決める大事な一枚です。
- 「志望動機が伝わらない」
- 「自己PRがぼんやりしている」
だけで、チャンスを逃す人も少なくありません。
通る履歴書は、読み手の視点を意識して、“ここで働きたい理由”と“どう貢献できるか”が明確です。
逆に、落ちる書類は「誰にでも当てはまる内容」や「雑さ」が目立ちます。
履歴書に不安がある方は、
PTOTSTワーカーやレバウェルリハビリのような転職支援サービスの添削サポートを使うのもおすすめです。



ひとりで悩まず、無料でプロの視点を借りて「伝わる履歴書」を目指しましょう。
\履歴書の添削もお願いできる!/
OTに人気の転職サイト3選